更新日
【指示待ち人間・指示待ち部下】は何がいけないのか

指示待ち部下の動かしかたについて以前ブログを書かせていただいたところ予想以上の反響がありました。
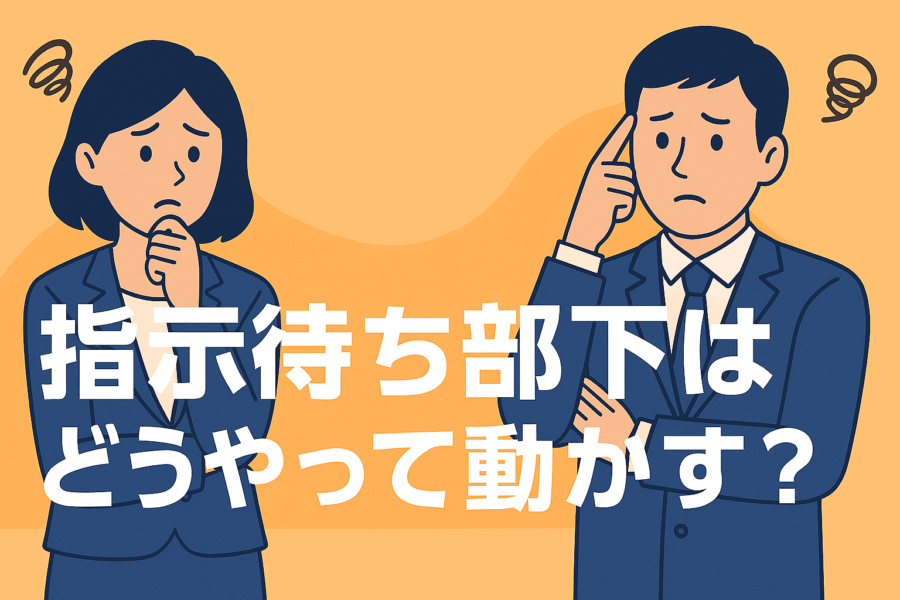
指示待ち部下を動かす必須条件!見落としがちな「指導の下地」とは?
指示待ち部下を動かす方法には、表彰制度による能動性の後押しや、本音でのコミュニケーション、評価制度の明確化などがあります。しかし、「ある…
その中で、指示待ち人間は別に指示さえ出せれはいいんでしょ?や、
余計な事されるより良い!と思うというお声もいただきました。
そのため、なぜ指示待ち人間が何がいけないのか、
指示待ち人間がいることで何が起きるのかについての記事を書こうと思いました。
分かりやすく7つのポイントに分けましたのでぜひ参考にしていただけますと幸いです。
生産性の低下
指示待ち人間が多い職場では、業務の進行が遅れがちになります。
自ら考えて行動することが少ないため、「指示を待つ時間」が発生してしまい、
結果として業務全体の生産性が低下する可能性があります。
特に、プロジェクトの進行においては、各メンバーが自発的に動くことが求められますが、
指示待ちの姿勢では「業務に必要な連携や報告・連絡・相談のスピード感」が失われます。
チームワークの悪化
指示待ち人間がいると、周りに自ら干渉せず指示を待つという状況が発生するため、
チーム内の「コミュニケーションが減少」する傾向があります。
自分から意見を出さず、指示を待つだけでは、他のメンバーとの連携が取りづらくなります。
これにより、「チーム全体の士気が低下」し、協力し合う雰囲気が損なわれることがあります。
上司の負担増加
指示待ち人間が多いと、上司はその人たちに対して頻繁に指示を出さなければならず、上司の負担が増加します。
上司は本来、戦略的な思考やチーム全体のマネジメントに集中すべきですが、
指示待ちの部下に対して時間を割くことで、本来の業務に支障をきたすことになります。
イノベーションの停滞
指示待ちの姿勢は、「創造性やイノベーションを阻害」します。
自ら考え、行動することが少ないため、新しいアイデアや改善策が生まれにくくなりますし、
先程も問題点に挙げたチームワークの悪化により意見交換による相乗的なイノベーション効果もなくなります。
特に、競争が激しいビジネス環境においては、イノベーションが企業の成長に不可欠ですが、
指示待ち人間が多いとその機会を逃してしまうことになります。
モチベーションの低下
指示待ちの姿勢は、本人のモチベーションにも悪影響を及ぼします。
自分から行動を起こさないことで、達成感や成長を感じにくくなり、結果として仕事に対する意欲が低下します。
また、周囲のメンバーもその姿勢に影響され、全体のモチベーションが下がることがあります。
これによりこの問題が企業全体に波及してしまい、「組織全体のモチベーション低下」へつながる可能性もあります。
人材育成の停滞
指示待ち人間が多い職場では、自己成長やスキルアップの機会が減少します。
自ら考え、行動することが少ないため、経験を積むことができず、結果として人材育成が停滞します。
企業にとっては、将来的なリーダーや専門家を育てることが難しくなり、
長期的な成長に悪影響を及ぼします。
特に、新卒社員を1、2名しか毎年採用しないような企業の場合は
その一名が指示待ちになってしまうと「1年分の育成自体が徒労」に終わってしまうケースも多いです。
組織文化の悪化
指示待ちの姿勢が蔓延すると、組織文化にも悪影響を与えます。
自発的な行動や意見交換が少ない環境では、社員同士の信頼関係が築きにくくなります。
また、失敗を恐れるあまり、リスクを取らない文化が根付くこともあります。
これにより、柔軟性や適応力が失われ、変化に対応できない組織になってしまう可能性があります。
結論
指示待ち人間が与える悪影響は多岐にわたります。
生産性の低下やチームワークの悪化、上司の負担増加など、
さまざまな側面から企業にとってのリスクとなります。
これを解消するために、社員が自発的に行動できるように指示を行っていく必要があります。
※組織の無料診断や採用のご相談はお気軽にしてください。
代表Facebookも更新しておりますのでこちらもぜひご覧ください。
<<代表Facebook>>
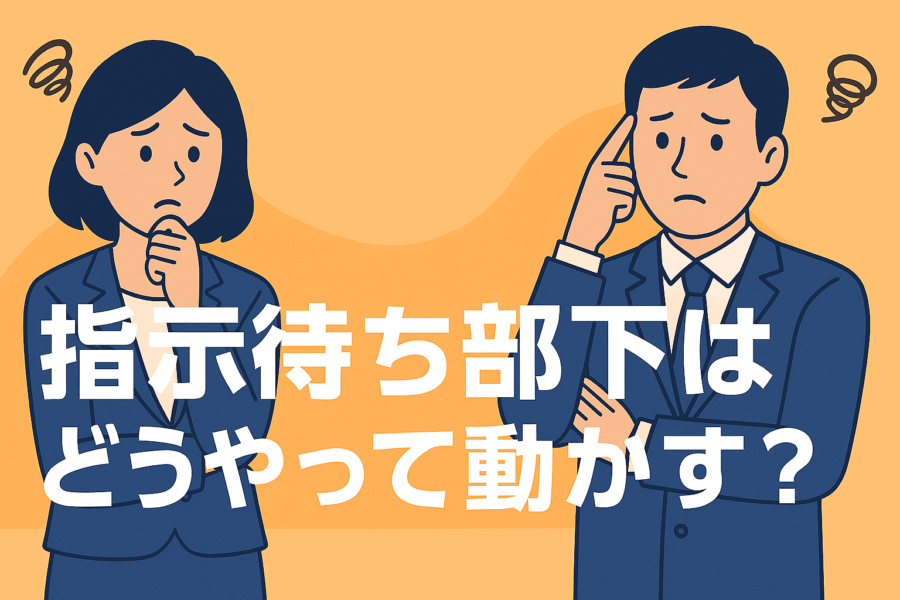
指示待ち部下を動かす必須条件!見落としがちな「指導の下地」とは?
指示待ち部下を動かす方法には、表彰制度による能動性の後押しや、本音でのコミュニケーション、評価制度の明確化などがあります。しかし、「ある…





