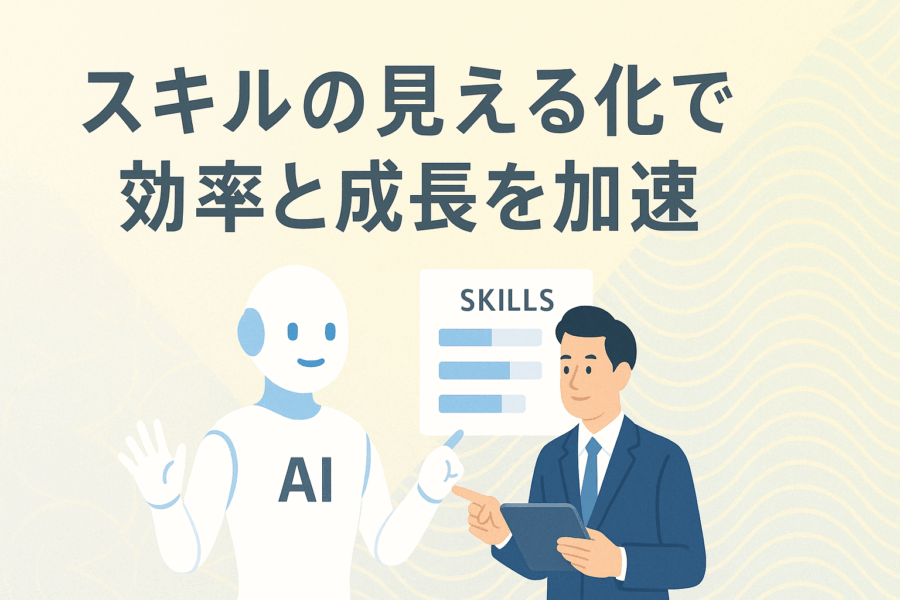更新日
マネジメント
人材採用
若手採用
【 若手採用 と 育成 の成功ポイント】効果的な戦略と実践方法

現代の企業にとって、 若手採用 と 育成 は持続的な成長を支える重要な要素です。
特にZ世代が職場に進出している今、従来の手法を見直し、時代に合った新しい取り組みを行う必要がございます。
本記事では、若手採用と育成の成功に欠かせないポイントと、具体的な戦略や実践方法を紹介させていただきます。
まずは、なぜ若手採用・育成が重要なのかについてです。
・Z世代の登場により、価値観や働き方が大きく変わりつつあり、この変化に適応できる企業が競争力を保てること。
・若手社員の離職率の高さは企業にとって大きな課題となっている。
・新しいメンバーを育成し、早期に戦力化することで、社内の活力を維持し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができること。
上記3点が主な要因だと思われます。
次に、効果的な戦略として、自社の魅力を如何にアピールするかが大切です。
若手は給与額だけでなく『成長機会』や『働きがい』を重視しています。
たとえばOJT制度や社内メンター制度を導入している企業は、求人票で“学べる環境”を具体的に示すことで応募率が向上しています。
また、ダイレクト・ソーシングの活用も一つの手法です。
直接的にターゲットとなる優秀な人材と接触する機会を増やし、より精度の高い採用活動を行いましょう。
最後に、育成の成功には継続的な学習文化の醸成が欠かせません。
若手社員が自ら学び成長できる環境を整え、モチベーションを高めることで、組織全体が一丸となって成長を遂げることが期待できます。
例えば、若手社員の成長計画を経営層が定期的にレビューする仕組みを導入すると、育成が現場任せにならず、組織全体で人材戦略を進められます。
その結果、離職率の低下や次世代リーダーの早期発掘につながります。
この記事を通じて、企業の成長に繋がる具体的なアプローチを学び、ぜひ実践に役立ててください。
Contents
現代の 若手採用 ・ 育成 の重要性
現代の企業にとって、若手採用と育成は非常に重要な課題です。特にデジタルネイティブ世代であるZ世代の登場により、
従来の手法では通用しない部分も多くなっています。
この世代は、テクノロジーに精通し、新しい価値観を持つため、採用・育成の手法を見直す必要があります。
昨今の問題点では冒頭でも示した通り、若手社員の離職率の高さが挙げられます。
若手社員は、キャリアアップや自己成長を重視する傾向が強い傾向があります。
そのため職場環境や成長機会が不足していると感じると、すぐに退職を考えるケースが多いです。
なので成長機会を多く与えることで早期に戦力化し、定着促進を図ることが企業の成長には欠かせません。
どちらにせよですが、企業が持続的に成長し続けるためには、若手社員の早期戦力化と定着がどうしても不可欠です。
若手社員を効果的に育成し、彼らが長期にわたって企業に貢献できるような仕組みを整えることで、企業全体のパフォーマンスや競争力も向上します。
時代が変わり、長期的に同じ企業に属することが当たり前ではなくなったこともあり、
【若手をつなぎとめるため】の若手採用・育成の重要性はますます高まっているのです。
若手採用 の現状と課題
若手採用の現状と課題は、企業が直面している大きな問題です。
若手採用 の現状
現代の若手採用の現状は、急速な変化とともに企業にとって大きな挑戦となっています。
特にZ世代と呼ばれる若手社員は、デジタル技術に精通し、新しい価値観を持っています。
このため、従来の採用手法では十分にアピールできない場合が増えています。
企業は、SNSやリモートインタビューなど、デジタルツールを活用した採用活動を展開する必要があります。
しかし、多くの企業がこの変化に対応しきれていないのが現状です。
さらに、新型コロナウイルスの影響で対面での採用活動が制限され、オンラインでの対応が求められるようになりました。
現在ではコロナウイルスは落ち着きましたがその余波は強く、Z世代特有とも言える【タイパ】の概念もあり、
オンライン等の対面よりも効率的に就職活動ができる企業が人気となっています。
そのため、企業は新しい面接形式や働き方に対応するための柔軟性と適応力が試されています。
若手採用 における課題
若手採用における課題として、前章でも上げさせていただいた高い離職率が課題となっている企業様は多くいらっしゃいます。
厚生労働省の調査によると、大卒新入社員の約34.9%が入社3年以内に離職しています(2021年卒)【厚労省】。
中小企業にとっては育成コストが無駄になるだけでなく、採用活動の再コスト発生につながるため、離職防止の取り組みは急務です。
この背景には、企業文化や仕事に対するミスマッチ、新しい環境への適応困難などが考えられます。
また、企業側が若手社員の期待値やニーズを十分に理解していないことも課題です。
例えば、JMAMの調査(2023年)によれば、Z世代の約6割が“安定した環境”を最も重視し、次いで“成長機会”を選択しています【JMAM調査】。
この結果は、若手がただ昇進や高収入を望むのではなく、“安心して挑戦できる環境”を求めていることを示しています。
が、これに対応できる環境が整っていない企業も少なくありません。
さらに、採用プロセス自体が若手にとって煩雑で時間がかかるものになっているケースも問題です。
これらの課題に対処するためには、柔軟な採用手法や効果的な育成プログラムの導入が求められています。
若手採用 を成功させるポイント
若手採用を成功させるためには、まず自社の魅力をしっかりとアピールし、次にダイレクト・ソーシングを積極的に活用することが重要です。
この2つのポイントを抑えることで、効果的な若手採用を実現することができるのです。
自社の魅力をアピールする
自社の魅力をアピールすることは、若手採用において極めて重要です。
特にZ世代の若手は、給与や福利厚生だけでなく、働く環境や社風、社会的な意義や価値観に重きを置く傾向があります。
例えば、社員同士のコミュニケーションが活発で、柔軟な働き方ができることを訴求することで、若手の関心を引きやすくなります。
具体例としては、公式ウェブサイトやSNSを活用し、社員のインタビュー動画や社内の様子を公開するのも有効です。
また、企業の成長ビジョンや社会的貢献活動を積極的にアピールすることで、企業の価値観にも共感してもらうことができます。
これにより、自社に魅力を感じてもらい、エントリー数の増加や採用後の定着率向上につなげることができるのです。
ダイレクト・ソーシングの活用
ダイレクト・ソーシングの活用は、若手社員を採用する際の効果的な手法の一つです。
従来の求人広告や求職サイトに頼るだけでなく、ダイレクトにターゲットとする若手人材にアプローチする方法です。
これには、LinkedInなどのプロフェッショナルなSNSを利用して、興味を持ちそうな候補者に直接連絡を取る方法があります。
こうした方法を取ることで、自社が求めているスキルや経験を持つ若手をピンポイントで探し出すことが可能となります。
さらに、手間はかかりますが、採用イベントやキャリアフェアに参加し、直接若手と交流する場を設けるのも良い手段です。
直接会うことで相手の人柄や考え方をよく理解でき、より適切な候補者を見つけることができるでしょう。
ダイレクト・ソーシングを活用することで、質の高い若手社員を効率良く採用することができるのです。
現代の若手社員の特徴
現代の若手社員は、特にデジタルネイティブであることが特徴的です。
技術の進化に敏感で、新しいツールやシステムを迅速に学習する能力があり、働き方にも柔軟性を求める傾向があります。
Z世代の特性と働き方
Z世代とは、1990年代後半から2010年代初頭に生まれた世代を指します。【Z世代とは/Wikipedia】
この世代はインターネットやスマートフォンが家庭に普及している環境で育ち、既にデジタル技術に精通していることが強みです。
Z世代の特性として、まず一つ目に挙げられるのは、技術の適応力が高いことです。
新しいデジタルツールやソフトウェアを使いこなすことに長けており、仕事の効率性を上げるために積極的に利用します。
二つ目に、働き方における柔軟性を重要視する傾向があります。
従来の9時から5時までの固定労働時間や、一か所にとどまる働き方には馴染みが薄く、
在宅勤務やフレックスタイム制など、場所や時間に縛られない働き方を好む傾向にあります。
三つ目に、環境意識が高いという点も特徴的です。
持続可能な社会の実現や、エシカルなビジネスプラクティスに強い関心を持ち、自らの仕事でもその価値観を反映させようとします。
最後に、Z世代は自己実現を重視する一方で、仕事とプライベートのバランスを取ることにも非常に敏感です。
このバランスを保ちながら、自分自身のスキルをどう伸ばせるかを常に考えているため、適切なフォローとフィードバックが求められます。
若手の価値観の変化
企業における若手社員の価値観は大きく変化してきています。まず、以前の世代に比べて成長機会を求める意識が強くなっており、
新しいスキルや知識を積極的に身につけ、自分自身のキャリアを主体的に作り上げていこうと考えています。
そして、多様性と包摂性の重要性を理解している点も特徴的です。
性別、国籍、年齢などの違いを尊重し、チームや職場環境において多様性を受け入れる姿勢が強調されています。
これは、企業文化としてのダイバーシティの推進にとって大きなポジティブ要素となります。
また、働きがいを求める声も増えており、単なる経済的報酬だけではなく、
仕事を通じて得られる満足感や達成感を重視する傾向があります。
これにより、社会貢献や自己実現の要素が組み込まれた仕事に対して強い関心を持つようになっています。
最後に、柔軟な働き方を求める風潮が増しています。
リモートワークの普及やフレキシブルな働き方に対する期待が高まる中で、企業側もこれに応じた働き方を提供することが求められています。
若手社員の育成の重要性
若手社員の育成は企業が持続的に成長するために欠かせない重要な要素です。早期に戦力化し、定着させることで、企業の競争力が向上します。
早期に戦力化するための施策
若手社員を早期に戦力化するための施策はいくつかあります。まず、入社後すぐに実践的な研修プログラムを実施することです。
このプログラムでは、業務に必要なスキルや知識を短期間で習得させることが重要です。
具体的には、現場でのOJT(オン・ジョブ・トレーニング)やロールプレイングを通じて、実践力を養うことが挙げられます。
また、メンター制度の導入も有効です。経験豊富な社員をメンターとして配置し、若手社員が業務上の悩みや疑問をすぐに解消できる体制を整えることで、早期に自信を持って業務に取り組めるようになります。
さらに、定期的なフィードバックと目標設定も戦力化を促進するポイントです。上司や同僚からのフィードバックをもとに、具体的な改善点や次の目標を設定することで、目標達成に向けたモチベーションを維持しやすくなります。
定着促進のための環境整備
若手社員の定着を促進するためには、働きやすい職場環境の整備が重要です。
まず、職場のコミュニケーションを活性化する取り組みが必要です。
例えば、定期的なチームミーティングや社内イベントを通じて、社員同士の絆を深める機会を提供することが有効です。
また、ワークライフバランスの改善も大切な要素です。
柔軟な働き方を導入し、若手社員がプライベートと仕事を両立しやすい環境を整えることで、離職率を低減させることができます。
さらに、キャリアパスの明確化も定着促進に寄与します。
若手社員が将来のキャリアに対して明確なビジョンを持つことができるように、キャリア形成支援やスキルアップの機会を提供することが重要です。このような環境整備によって、若手社員が長期的に会社で活躍できるようになります。
若手社員の育成方法
若手社員の育成方法については、まず効果的な研修プログラムの導入、オフ・ジョブトレーニング(OJT)の実施、自律学習の促進が重要です。
効果的な研修プログラムの導入
効果的な研修プログラムの導入は若手社員の成長に大きな影響を与えます。まず、研修内容は実践的であり、現場での応用が可能なスキルの習得に重点を置く必要があります。例えば、新人研修ではビジネスマナーやコミュニケーションスキルの基礎から、専門スキルに至るまで幅広くカバーすることが求められます。
研修プログラムは定期的に見直しを行い、最新の業界トレンドや技術に対応する内容に更新することも重要です。これにより、若手社員が常に最新の知識とスキルを身につけることができます。また、研修の進捗状況を定期的に評価し、フィードバックを行うことで、個々の成長に合わせたサポートが可能となります。
最後に、研修の効果を高めるために、実践的な演習やシミュレーションを取り入れることが有益です。これにより、参加者はリアルな業務環境での課題解決力を養うことができ、現場での即戦力としての能力が向上します。このような研修プログラムの導入は、若手社員のスキルアップとモチベーション向上につながります。
オン・ジョブトレーニング(OJT)
オン・ジョブトレーニング(OJT)は、実際の業務を通じてスキルを習得する方法です。新入社員には、業務の一環として先輩社員が付いて教えることで、実績を基にした実践的な学びが得られます。これにより、若手社員が即戦力として活躍できる環境が整います。
OJTの効果を高めるためには、計画的な指導が必要です。例えば、OJT開始前に学習目標を明確に設定し、達成すべき目標を具体的に示します。これにより、若手社員は何を学ぶべきかを明確に理解しやすくなります。
また、OJTを担当する先輩社員に対しては、指導技術を向上させるための研修も提供することが重要です。指導者が適切なフィードバックを行い、若手社員が自己の成長を実感できるようサポートすることで、モチベーションの向上にもつながります。定期的な進捗確認と評価を行い、フィードバックを共有することも忘れてはいけません。これらの取り組みにより、OJTの効果を最大限に引き出すことができます。
日常業務の中で学ぶOJTに加え、外部研修やeラーニングなどのOff-JTを組み合わせることで、若手の成長スピードは大きく高まります。
OJTについては、他記事でも解説をしておりますので是非ご覧ください
自律学習を促進する方法
自律学習を促進することは、若手社員の成長にとって不可欠です。自律学習が進むことで、社員自身が主体的に知識を吸収し、専門スキルを深めることができます。まず、自律学習のためのリソースを提供することが重要です。オンラインコースやeラーニングプラットフォーム、教材などを社員が自由に利用できる環境を整えましょう。
自律学習を支援するためのコミュニティも有益です。例えば、社内で勉強会やワークショップを定期的に開催することで、若手社員同士が互いに学び合う機会を提供します。これにより、知識の共有が進み、社員のモチベーションも向上します。
さらに、学んだ内容を実務に生かすフォローアップを忘れずに行うことが重要です。例えば、学習後に具体的なプロジェクトに参加させることで、実際の業務で学びを応用しやすくなります。また、自己学習の進捗を管理し、定期的に目標設定とその達成状況をチェックすることで、継続的な成長を支援します。
以上のような方法で自律学習を促進することで、若手社員が主体的に成長し、スキルを高める環境を作ることができます。
育成担当者の役割とスキルアップ
育成担当者は若手社員の成長をサポートし、彼らが持つポテンシャルを最大限に引き出す重要な役割を担います。彼らの指導力やコミュニケーションスキルの向上は、チーム全体の成果に直結し、企業の競争力を高める鍵となります。
指導力向上のための研修
指導力向上のための研修は、育成担当者にとって非常に重要です。まず、体系的な指導法を学ぶためのプログラムが求められます。例えば、ロールプレイング形式の研修により、実際の指導シチュエーションを模擬体験することができます。この形式では、現実の問題に直面した際の対処法を具体的に学ぶことができ、育成担当者は自信を持って指導に当たることができます。
次に、経験豊富なメンターからのフィードバックも重要です。自身の指導方法についてのフィードバックを受けることで、無意識のうちに行っている指導の癖や改善点に気づくことができます。これにより、指導方法のブラッシュアップが図られます。
また、指導力向上の一環として、心理学やカウンセリングの基本知識を学び、人間関係の構築や問題解決のスキルを身につけることも有効です。これにより、若手社員のメンタルサポートやパフォーマンス向上に貢献することができます。
最後に、チームビルディング研修やアウトドアイベントなどを通じて、実際の職場環境でのコミュニケーション能力を高める活動も推奨されます。育成担当者がリーダーシップを発揮し、チーム全体をまとめる力を養うことで、若手社員の信頼を得ることができます。
コミュニケーションスキルの強化
コミュニケーションスキルの強化は、育成担当者にとって欠かせない要素です。まず、聞き上手になることが大切です。育成担当者が若手社員の声に耳を傾け、彼らの質問や悩みに対して的確なアドバイスを行うことが求められます。このスキルは、信頼関係の構築に直結し、若手社員の成長をサポートします。
次に、クリアでわかりやすい指導を心がけることが重要です。専門用語や複雑な説明を避け、平易な言葉で具体的な指示を提供することが、若手社員の理解を深めます。また、フィードバックを行う際には、具体的な例を挙げてポジティブな面と改善点を公平に伝えることが効果的です。
さらに、非言語コミュニケーションのスキルも見逃せません。ボディランゲージや表情の変化は、言葉以上に多くを伝えることがあります。例えば、笑顔で接することや、真摯な態度で話を聞くことによって、若手社員は安心感を持って仕事に取り組むことができます。
最後に、定期的なコミュニケーションチェックインを行うことが推奨されます。定期的に面談を実施することで、若手社員の悩みや問題を早期に察知し、適切な対応策を講じることができます。これにより、離職率の低下やモチベーションの維持にもつながります。
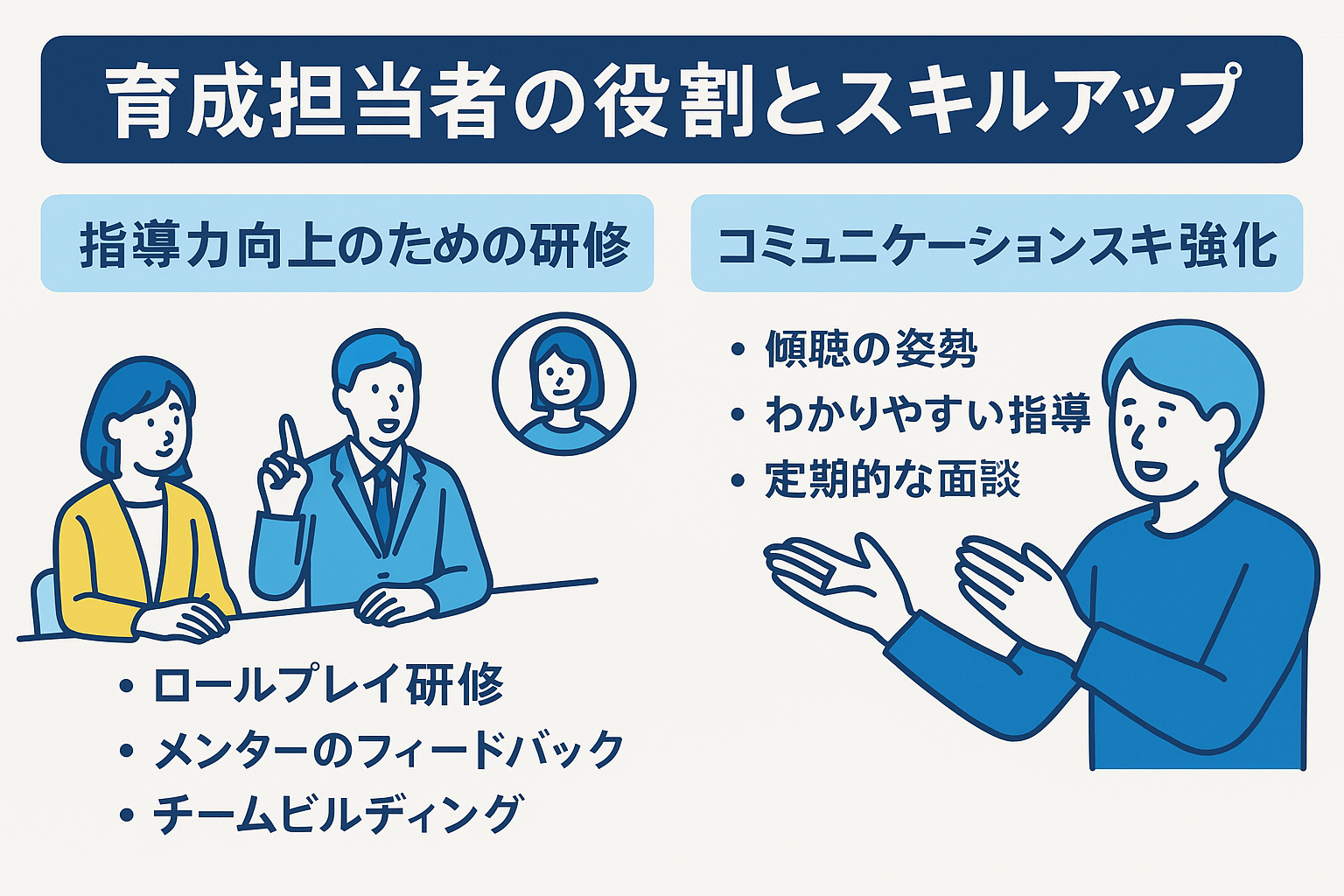
成功事例から学ぶ 若手採用 ・ 育成
成功事例は、若手社員の育成において非常に有益な学びを提供します。成功した企業の具体的な施策やアプローチを学ぶことで、自社でも同様の成果を期待できる方法を見つけられるでしょう。次に、他社の成功事例とその秘訣について詳しく見ていきます。
他社事例紹介: 若手採用 ・育成成功の秘訣
レバレジーズ株式会社
概要
創業2005年。IT・人材・医療など複数事業を持つメガベンチャー。若手の抜擢が非常に活発な企業です。
若手育成・採用で成功している具体的な取り組み
- 平均年齢が若く、リーダー職を20代が担うケースが多い。入社3年目以下でチームリーダーになる例も多数。
- 自由と責任を持たせるカルチャー。若手が意思決定にも関わり、裁量をもって動ける環境を整えていて、経験を積む機会を多く提供している。
- 新規事業を積極的に立ち上げ、その中で若手が事業の立ち上げ〜運営に関わるポジションにつくことが可能。ゼロからの事業作りの体験を通じて多様なスキル・判断力を養っている。
- 働きがい・従業員満足度の高さを社員アンケート等で評価されており、「若手ランキング 大規模部門第1位」なども獲得している。
学びになる点
- 若手のキャリアパスを明示し、リーダー/事業責任を早く任せることでモチベーションと成長スピードを高める。
- 新規事業が次々とできるので、若手が挑戦できるステージが多い。
- 担当範囲・責任の幅を持たせて育成することで、自律性・判断力を鍛える。
ソウルドアウト株式会社
概要
デジタルマーケティング領域で、中小・地方企業の支援を全国規模で行っているベンチャー。若手育成を採用戦略にも組み込んでいる企業です。
若手育成・採用での特徴的な取り組み
- 将来の経営者候補 (“CxO候補”) を採用するコースを設けており、管理会計・経営戦略・バックオフィスおよび事業サイドをローテーションするなど、多面的に経営視点を持てる経験を積ませるキャリアパスがある。
- 新卒採用でも全国から採用をし、地方出身者も含めて広く人材を集めている。入社後研修制度も整備されており、配属前の研修を通じて基礎/心構えを共有する機会を持っている。
- アンバサダー制度など、学生との接点や発信を重視していて、若手や将来の候補者が会社や業界を理解しやすいような取り組みをしている。これも若手採用・育成の基盤を強める要素。
学びになる点
- “将来像(CxOなど)”を見せる採用設計をすることで、若手にとって魅力的なキャリアの道筋を示す。
- 入社前/配属前の研修で、カルチャーや会社全体の仕組み・価値観を共有することがミスマッチ防止につながる。
- 地方採用やアンバサダー制度など、多様なバックグラウンドの人材を採る取り組みが組織に新しい視点を持ち込む。
株式会社 IVRy(アイブリー)
概要
対話型音声AI SaaS を提供し、比較的若い会社。急成長中。
若手育成・採用での特徴的な取り組み
- 組織開発部門の強化を進めており、人事制度・育成基盤を「これから成長させていく」フェーズで投資している。即ち、若手をただ雇うだけでなく、成長する環境を整備中。
- 採用チャネルやポジション設計で「一人目人事」などの役割を与えることで、若手が大きな裁量を持って働ける機会があると社員が語っている。
- 急拡大中の組織なので、未整備な部分も多いが、そこを「整えていく過程」そのものが若手育成の場になっている。自分で仕組みを作っていく経験ができる。
学びになる点
- 成長ステージが早いベンチャーでは、「環境を整備するフェーズ」も含めて若手に参加させることで育成機会を創出できる。
- 裁量のある役割を与えることがモチベーションや成長速度に大きく寄与する。
- 採用だけでなく、制度や組織のデザインも同時並行でやっていく必要がある。
失敗事例とその対策
若手社員の育成において失敗した事例からも、多くの学びを得ることができます。まず、D社のケースでは、一般的な研修プログラムに依存しすぎていました。標準的なトレーニングだけでは、各社員の個別のニーズに対応できず、結果的にモチベーションの低下を招くこととなりました。個別のフォローアップやカスタマイズされた育成計画が必要です。
E社においては、フィードバック文化の欠如が問題となりました。若手社員が自身の進捗や課題についてフィードバックを受けられない状況では、自己改善の機会を失い、成長が停滞してしまいます。E社は、フィードバックを定期的に行う仕組みを導入することで、この課題を克服しました。
さらに、F社の事例では、職場環境の整備が不十分だったことが失敗の要因となりました。長時間労働やコミュニケーション不足が常態化していたため、若手社員の離職率が非常に高くなりました。これに対処するために、F社はフレキシブルな働き方を推進し、オープンなコミュニケーションを促進するための環境づくりに取り組みました。これらの失敗事例から学び、同じ過ちを繰り返さないよう対策を講じることが重要です。
まとめ: 若手採用 と 育成 の成功ポイント
若手社員の採用と育成は、企業の持続的な成長と成功のために重要な要素です。
特にZ世代というデジタルネイティブ世代をターゲットにした採用戦略と育成方法は、新しい価値観や働き方に対応する工夫が必要です。
まずは、自社の強みや価値を明確にし、若手社員にとって安定性及び成長性の2つを感じられる環境を提供することが求められます。
なので、ダイレクト・ソーシングの活用や効果的な研修プログラムの導入、オフ・ジョブトレーニング(OJT)を通じて若手社員のスキルを早期に戦力化する施策も不可欠です。
さらには、自律学習を促進する方法を取り入れることで、継続的な学習文化を作り、社員のモチベーションを維持することができます。
育成担当者の指導力向上やコミュニケーションスキルの強化も忘れてはならないポイントです。
成功事例から学び、他社の成功の秘訣や失敗事例を参考にすることで、自社の育成戦略を改善し、実践に活かすことができます。
これらのポイントを押さえることで、若手社員の戦力化と定着率の向上を効果的に達成できるでしょう。
若手採用 のお悩みはTsumuguへお任せください
若手採用・育成に関する取り組みは、企業の未来を左右する重要なテーマです。とはいえ、自社に合った最適な戦略を見つけるのは簡単ではありません。
「どこから着手すればよいか分からない」「具体的な施策を検討したい」といったお悩みがある企業様向けに、私たちは貴社の課題に合わせたサポートをご提案しています。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽に以下のフォームよりお問い合わせください。
※組織の無料診断や採用のご相談はお気軽にしてください。
LinkedInも更新しておりますのでこちらもぜひご覧ください。
<<代表LinkedIn>>