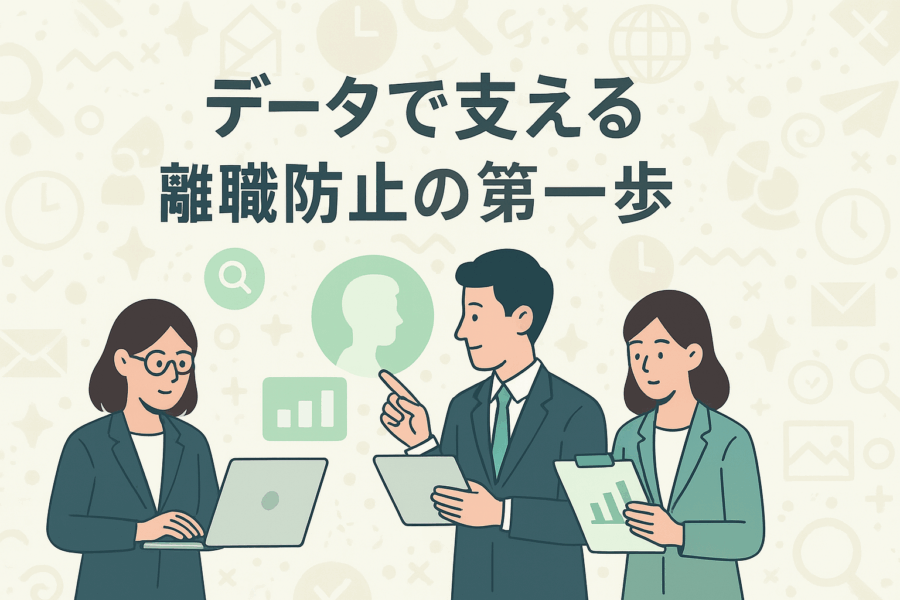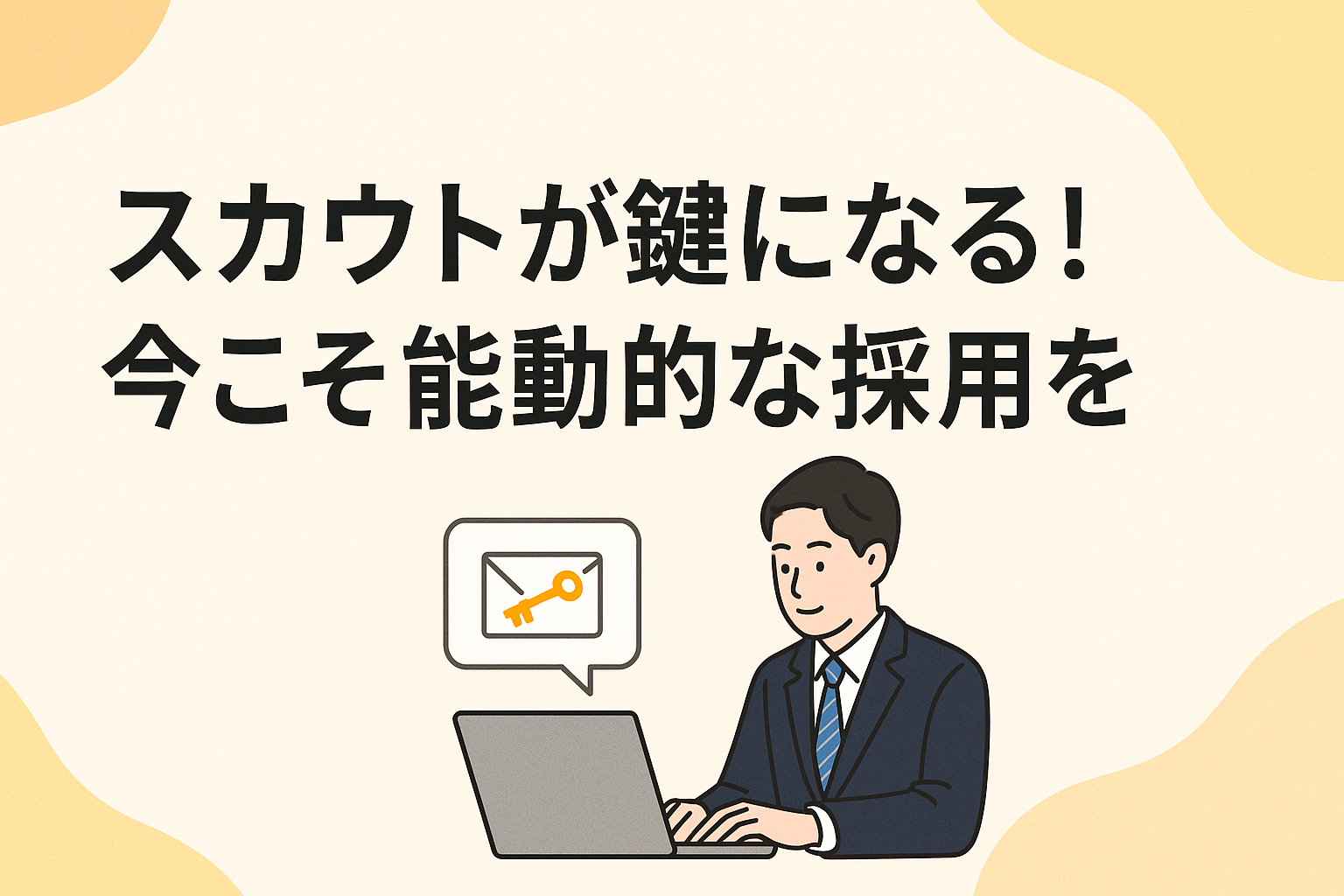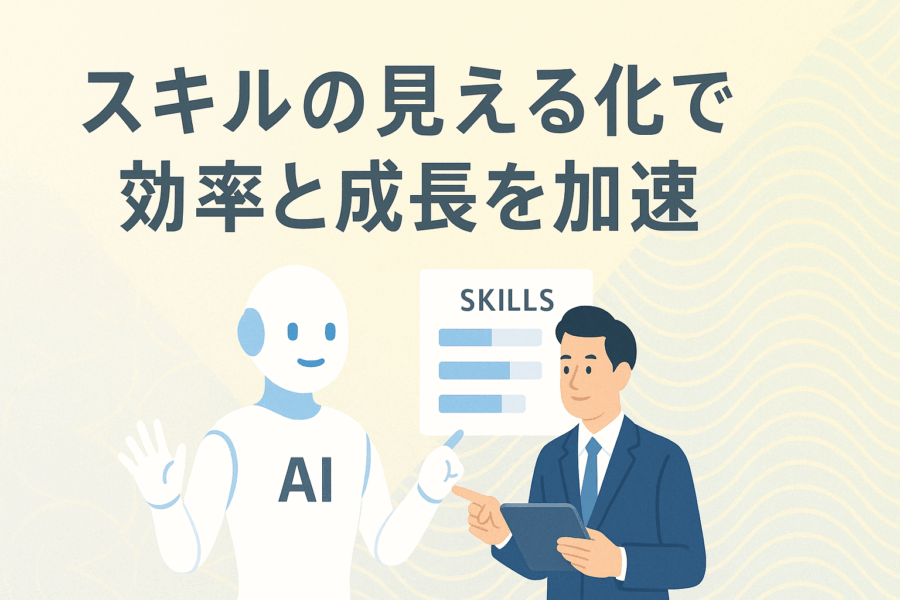更新日
エンゲージメント
マネジメント
従業員エンゲージメントを高める“ 心理的安全性 ”の作り方とは?
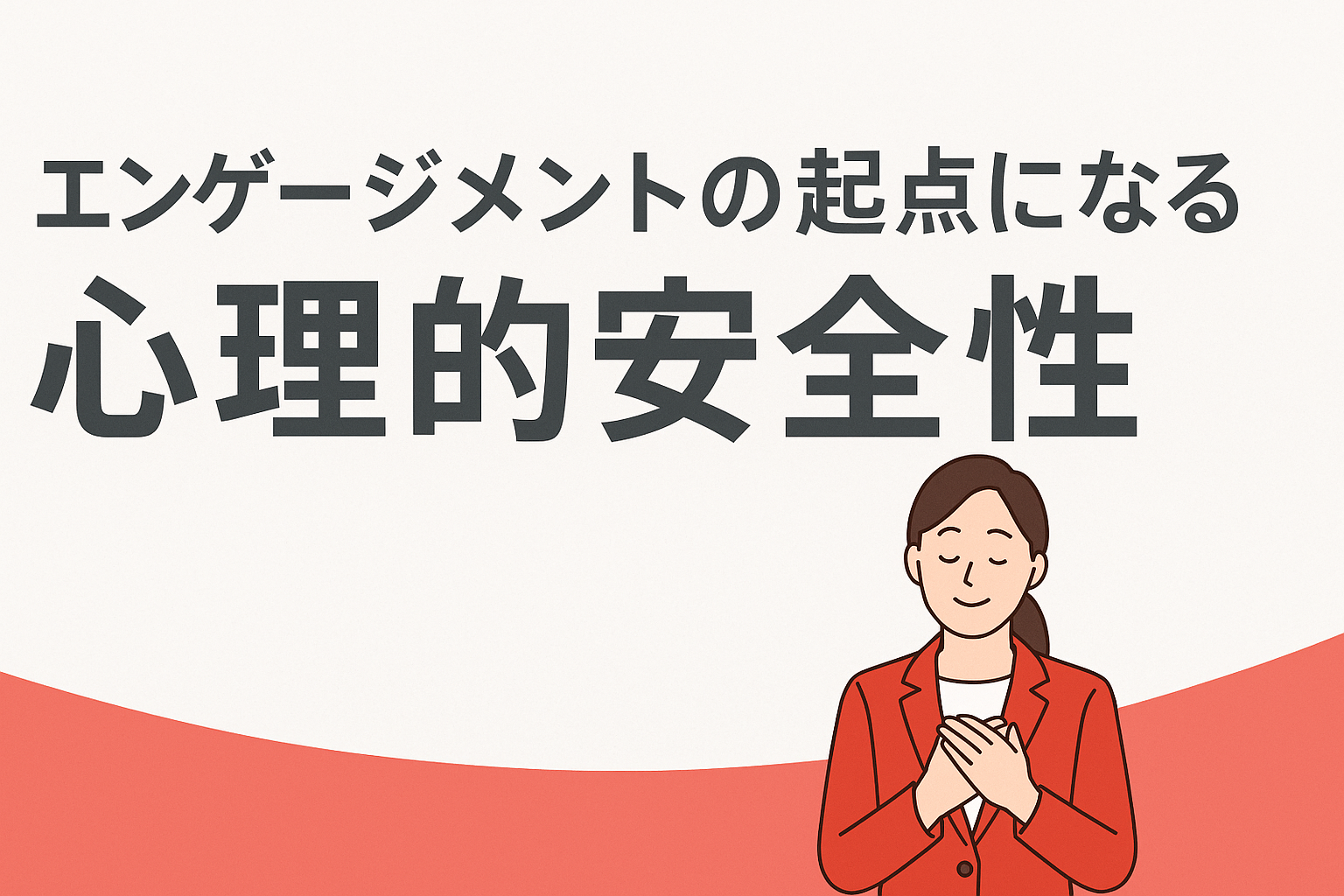
職場の 心理的安全性 をどう高めればよいのか、あるいは従業員エンゲージメントをどう向上させるか――こうした課題に悩む企業は少なくありません。
心理的安全性 とは、従業員が自分の考えや意見を安心して発言でき、失敗を恐れずに挑戦できる職場環境を指します。これが確保されることで、組織内のコミュニケーションが活性化し、新たなアイデアが生まれやすくなります。その結果、パフォーマンス向上や離職防止にもつながると考えられています。
一方、エンゲージメント向上は、従業員が仕事や組織に対して主体的に関わる姿勢を引き出すための取り組みです。両者は密接に関係しており、組織が意識的に働きかけることで、より働きやすい職場づくりやチームの成果向上が期待できます。
このページでは、 心理的安全性 を高めるための具体策や、エンゲージメントを促進する実践方法について紹介します。また、 心理的安全性 が不足している職場に見られる特徴や、それを改善するために企業が取るべき行動、実際に取り組んで成果を上げた企業の事例にも触れながら、職場づくりのヒントをお届けします。
これらを参考に、自社に合った改善の方向性を見つけ、具体的な施策へとつなげていただければと思います。
Contents
心理的安全性 とは?
心理的安全性 は、心理学者エイミー・エドモンドソン氏によって提唱された考え方で、職場で個人が自分の意見やアイデアを率直に伝えられる状態を指します。たとえば、発言が否定されたり、批判されたりする不安が少ない環境では、従業員は安心して行動することができます。
エドモンドソン氏の研究では、 心理的安全性 の高いチームでは協働や学習行動が活発になり、結果的にパフォーマンスが向上する傾向があることが示されています。
また、Googleの「プロジェクト・アリストテレス」でも、チームの効果性に最も影響を与える要因として心理的安全性が挙げられました。
このように、 心理的安全性 は個人の安心感だけでなく、組織全体の成果にも深く関わる重要な要素です。
なぜ今“心理的安全性”が注目されているのか?
近年、テレワークの拡大や多様な働き方の浸透により、組織内のコミュニケーションのあり方が大きく変化しています。従来のように顔を合わせて気軽に話すことが難しい状況では、安心して発言できる雰囲気がないと、意見のすれ違いや孤立が起こりやすくなります。
また、チームの構成が多様化する中で、価値観や背景の違いを尊重しながら協働するためにも、心理的安全性の確保は欠かせません。単なる「仲の良さ」ではなく、立場や経験にかかわらず意見を出し合える関係づくりが、今の組織にとってより重要になってきています。
働き方の多様化と心理的安全性の関係
プロジェクト型の仕事やフレックスタイム制度、ハイブリッドワークといった柔軟な働き方が浸透する中で、メンバー間の信頼構築や意見交換の機会が減少しがちです。こうした環境では、意図しなくても「聞きにくい」「頼みにくい」と感じる瞬間が増えることもあります。
そのため、リモート会議では誰もが話す機会を持てるように設計したり、発言を歓迎する姿勢をリーダーが示すなど、仕組みや文化の面から心理的安全性を後押しすることが必要です。
安心して意見を共有できる状態が保たれることで、チーム全体の関係性やパフォーマンスにも良い影響を与えることが期待されます。
心理的安全性とエンゲージメントの関係性
従業員エンゲージメントとは、仕事や組織に対して自発的に関与し、貢献したいという意欲を持っている状態を指します。心理的安全性の高い環境では、「発言しても大丈夫」「相談しても受け入れられる」といった安心感が生まれ、業務に対する前向きな姿勢や主体性も育ちやすくなります。
このような環境では、ミスを隠すよりも共有して早期に対応する文化が育ち、信頼や協力関係が生まれやすくなります。結果的に、個人だけでなくチーム全体のエンゲージメントが高まり、生産性や定着率の向上につながることも少なくありません。
心理的安全性が高い組織のメリット
職場での心理的安全性が高まると、日々のコミュニケーションや働き方に徐々に変化が現れます。意見を言いやすい雰囲気が整うことで、従業員の関与度、すなわちエンゲージメントが高まり、結果として組織全体の活力や成果にも良い影響をもたらします。ここでは、心理的安全性が与える主なメリットを、いくつかの視点から見ていきます。
安心して働ける環境がエンゲージメントを育てる
心理的に安心できる職場では、「言ってもいい」「聞いてもらえる」という信頼感が生まれます。このような環境下では、従業員が自分の考えや気づきを伝えることに前向きになり、日々の業務に対する関与が深まっていきます。
たとえば、上司や同僚とのやりとりで否定されずに受け止められる経験が積み重なると、次第に職場への信頼や自発的な行動が生まれやすくなります。
加えて、日常的なフィードバックやちょっとした成果をチームで共有し合う仕組みも、エンゲージメントを高めるうえで効果的です。こうした取り組みが、従業員の意欲やモチベーションを下支えします。
定着率の向上とメンタルの安定
心理的安全性のある職場では、「この場所で働き続けたい」と感じる従業員が増える傾向にあります。
安心して悩みや課題を話せる環境があれば、問題が深刻化する前に対応できるため、心身の負担を抱え込みにくくなります。
また、先のキャリアについても周囲と相談しながら考えられる土壌があることで、個人の将来像と組織の方向性とをすり合わせやすくなります。
こうした積み重ねが、従業員の定着や長期的な働きがいにもつながっていきます。
チームの創造性や学習速度の向上
意見を出すことに不安がない職場では、新しいアイデアが自然と生まれやすくなります。誰かの発言が引き金となって議論が深まり、そこから実際の改善や新たな価値が生まれるケースも少なくありません。
また、心理的安全性のあるチームでは、「間違えてもいい」「わからないことは聞いていい」という共通認識があるため、情報共有や相互支援が活発になります。その結果、チーム内での学びが循環し、組織としての成長速度も高まっていきます。
創造力と学習力の土台には、こうした安心感が欠かせないのです。
心理的安全性の低い職場に見られる兆候
心理的安全性が保たれていない職場には、いくつか共通する“気づきのサイン”があります。日常のコミュニケーションや働き方の中でその兆候を見逃さずに捉えることは、職場環境の改善や従業員エンゲージメントを維持するうえで欠かせません。
以下では、よく見られる代表的なパターンをご紹介します。
声を上げづらい空気
会議や日常のやりとりの中で、誰も意見を言いたがらない場面が増えているとしたら、それは注意が必要です。
「何を言っても否定されるのでは」「余計なことを言うと損をするかもしれない」――そうした不安があると、従業員はリスクを避け、沈黙を選ぶようになります。
結果として、課題に対する建設的な指摘や改善案が出にくくなり、組織の成長機会を逃してしまう恐れがあります。
失敗を避ける風土
新しい取り組みへの挑戦が見られず、いつも「前例どおり」「無難なやり方」に終始している場合、それは心理的安全性が損なわれているサインかもしれません。
「失敗=評価が下がる」といった認識が広がっていると、従業員はリスクを取ることを避け、結果としてイノベーションや改善の芽が出にくくなります。
こうした環境では、働く側の手応えも得られにくく、エンゲージメントの低下にもつながりかねません。
信頼関係の不足
職場での情報共有が滞っていたり、連携がうまくいっていないと感じるときは、チーム内の信頼に課題がある可能性があります。
「相談しても取り合ってもらえない」「ミスを報告しにくい」――このような不安があると、従業員同士の協力関係も築きにくくなります。
信頼が損なわれた状態では、チーム全体の雰囲気がギスギスしやすくなり、結果的に業務効率や人材の定着率にも悪影響が出ることがあります。

心理的安全性を高めるために企業ができること
心理的安全性は、一朝一夕に築けるものではありません。職場に関わる一人ひとりの行動や姿勢の積み重ねが、少しずつ安心感のある環境をつくっていきます。ここでは、企業として心理的安全性を高めるために実践できる取り組みを、3つの視点からご紹介します。
オープンコミュニケーションの奨励
従業員が率直に話せる場があるかどうかは、心理的安全性を測るうえでのひとつの指標です。たとえば、1on1ミーティングや意見交換の場を定期的に設けることで、「話してもいい」という意識が自然と育ちます。
そのためには、まずリーダー自身がオープンな姿勢で臨むことが重要です。自分の考えや課題も共有し、相手の意見を否定せずに受け止めることが、信頼関係のベースになります。
こうしたやり取りの積み重ねによって、従業員は自分の声が尊重されていると実感でき、職場への関与意識やエンゲージメントの向上にもつながっていきます。
リーダーシップとマネジメントの重要性
心理的安全性のある組織づくりには、リーダーの姿勢が大きな影響を与えます。
たとえば、メンバーからの報告に真摯に耳を傾けたり、ちょっとした意見にも「ありがとう」と反応を示したりすることが、安心感の土台になります。
また、「完璧でなくていい」という前提を共有し、失敗や迷いも対話の中で扱えるようになると、チーム全体が挑戦を前向きに捉えるようになります。こうした風土は、従業員の自主性や意欲を引き出し、組織としての一体感も高めていきます。
失敗への対応
誰にでもミスや失敗はあります。そのときにどう向き合うかは、職場の文化を大きく左右します。
たとえば、プロジェクトの振り返りの場で「うまくいかなかったこと」をあえて共有し、そこから得られた学びをメンバー全員で言語化する――そんなプロセスを取り入れることで、「失敗しても大丈夫」という感覚がチームに広がります。
リーダー自身が、自らの失敗談を開示しながら「学びに変える姿勢」を見せることも効果的です。こうした雰囲気が根付くことで、従業員は安心して新しいことに挑戦できるようになり、長期的には創造性やエンゲージメントの向上にもつながります。
現状を見える化するチェックリスト
自社の心理的安全性がどれだけ確保されているかを確認するには、客観的な視点が役立ちます。以下は、職場環境を見直す際のチェック項目です。
- 従業員が意見を自由に発言できる場がある
- フィードバックが対話的かつ前向きに行われている
- 失敗に対して寛容な姿勢が共有されている
- リーダーが率先して情報を開示している
- 上司との1on1が定期的に実施されている
- チーム内での対話や意見交換が習慣化している
- 否定されずに意見が受け止められる雰囲気がある
- メンバーの成長を支援する関わり方がされている
- 従業員がリスクをとっても評価される環境がある
- 成功・失敗を問わず、振り返りと共有の機会がある
このようなチェックを通じて、心理的安全性の状態を把握し、どこに改善の余地があるかをチームで話し合ってみるのも一つの方法です。従業員一人ひとりが安心して力を発揮できる職場づくりは、組織の持続的な成長にも直結します。
エンゲージメント向上の実践方法
従業員エンゲージメントとは、仕事や組織に対して主体的に関わろうとする意欲や姿勢を指します。このエンゲージメントを高めるには、土台として心理的安全性のある職場環境が欠かせません。
安心して発言し、挑戦できる状態が整ってこそ、従業員は仕事に意味を見出し、自らの力を活かそうとする意欲が生まれます。
ここでは、エンゲージメント向上に向けた具体的な施策をいくつかの観点からご紹介します。
※エンゲージメントサーベイについては別の記事もございますのでこちらもあわせてご覧ください。
組織カルチャーと職場環境の改善
企業の風土や価値観は、従業員の行動や意識に大きな影響を与えます。特に「声を出しやすい雰囲気があるか」「お互いを尊重する姿勢があるか」といった職場の空気感は、心理的安全性にも直結します。
たとえば、雑談も交えながら意見を交換できる場があったり、リーダーが部下の話にしっかり耳を傾けたりといった日常のやりとりが、自然と信頼関係を深めていきます。
また、リモートワークが普及した今、オンライン上での対話の質や頻度も重要になっています。
1on1ミーティングや定期的なフィードバックの時間を確保することは、孤立を防ぎ、働くうえでの不安を取り除く一助となります。
こうした環境整備が進むことで、従業員は安心して業務に取り組むことができ、結果としてエンゲージメントが高まっていきます。
ワークハピネスの促進
仕事のやりがいや充実感、いわゆる「ワークハピネス」は、エンゲージメントと深い関係があります。
自分の得意分野や興味に合った業務に取り組めているか、成長の実感を得られているか、といった要素が積み重なることで、仕事に対する前向きな姿勢が育まれます。
具体的には、スキルアップの機会を提供したり、業務の中で裁量を持てるようにしたりすることで、自分が価値を発揮できていると感じられるようになります。
また、心身の健康を維持するための支援体制(例:ストレスケアや相談窓口の整備)も、長期的な安心感につながります。
さらに、チームビルディングのイベントやちょっとした感謝を伝え合う文化を取り入れることで、職場内のつながりや一体感が強まり、より働きがいのある環境が生まれていきます。
エンゲージメント測定の方法
取り組みを実行しても、それが従業員のエンゲージメントにどう影響しているのかを把握できなければ、改善にはつながりません。
そのためには、定期的な調査や対話を通じて、現場の声を拾い上げる仕組みが必要です。
代表的な方法としては、匿名での従業員サーベイや1on1ミーティング、業務に関する定期的なフィードバックの場などがあります。
これらを通じて、モチベーションの変化や組織に対する期待・不満といった“見えにくい感情”を拾い上げることが可能になります。また、離職率や評価面談での傾向などのデータもあわせて分析することで、組織全体のエンゲージメントの状態を立体的に捉えることができます。
継続的に現状を可視化し、小さな改善を積み重ねることで、従業員の関与度を高め、より働きがいのある職場づくりにつなげることができます。
成功企業に学ぶ ― トヨタの心理的安全性への取り組み
心理的安全性の重要性が広く認識される中、すでに実践的な取り組みを進めている企業も少なくありません。なかでも、トヨタ自動車は、製造現場での改善文化と信頼のあるチームづくりを両立させることで、心理的安全性を組織の土台に据えてきた企業のひとつです。
トヨタの成功事例
トヨタ自動車は、生産性と人材活用の両立に成功している企業の一つです。その背景には、単なる制度や施策だけではなく、現場起点の文化と組織づくりの工夫があります。
中心にあるのは、トヨタ生産方式(Toyota Production System:TPS)です。
「ジャスト・イン・タイム」
「自働化(じどうか)」
この2本柱からこの方式は成り立ち、ムダの排除と品質の自律的な管理を追求する仕組みです。特徴的なのは、これらが単なる工程管理ではなく、従業員一人ひとりの主体性に根ざして運用されている点です。
たとえば、現場では改善提案が日常的に行われ、作業者自身が「もっと良くするにはどうすればいいか」を考えることが奨励されています。その提案が実際に反映されることで、「自分の声が組織に届いている」という実感が生まれ、自然と仕事への関与度が高まります。
また、トヨタでは従業員との対話も重視されており、現場のフィードバックを経営や現場マネジメントに反映する取り組みが根づいています。形式的な意見収集ではなく、日常的な1on1や朝会のような場面を活用して、率直なやり取りを可能にする工夫が施されています。
さらに、従業員のキャリア形成にも力を入れており、成長の機会を得ながら自らの専門性を磨ける環境が整っています。職務ローテーションや教育体系の充実などを通じて、「成長実感」を持ちながら働けることが、長期的な定着とエンゲージメントの維持に繋がっています。
このように、トヨタはTPSの仕組みを「効率のための管理手法」としてではなく、「従業員が力を発揮できる仕組み」として位置づけています。その結果、現場の声が生きた組織運営が可能になり、従業員の意欲・関与・信頼感が高まる好循環が生まれているのです。
チーム単位でできる!現場での小さな工夫
心理的安全性を高めるといっても、特別な制度や施策が必要なわけではありません。むしろ、日々のチーム運営の中でできる、ちょっとした工夫の積み重ねが鍵になります。ここでは、現場レベルで実践しやすい3つの工夫をご紹介します。
1on1の質を高める
1on1ミーティングは、チーム内での信頼関係を築くうえで欠かせない手段ですが、ただ「定期的に開催する」だけでは十分とはいえません。大切なのは、1on1が従業員にとって「安心して本音を話せる場」になっているかどうかです。
まず、話す内容の目的をお互いに共有しておくことがポイントです。
「最近どう?」では終わらず、あらかじめテーマを決めておくと、短時間でも充実した対話につながります。
また、話を聴く側の姿勢も重要です。相手の話に割り込まず、じっくり耳を傾けることで、「この場ではきちんと向き合ってもらえている」という安心感が生まれます。
「最近困っていることある?」など、相手の視点に寄り添った問いかけをすることで、本人も気づいていなかった課題や気持ちが引き出されることもあります。こうした信頼の積み重ねが、チーム全体の心理的安全性とエンゲージメントを高める土台になります。
チーム内ルールの明文化
チームがうまく機能している時は、暗黙の了解や感覚的なやりとりでもなんとかまわりますが、環境が変化したときにはその「当たり前」が通じなくなることもあります。
そこで有効なのが、チーム内のルールや共通認識をあえて言葉にしてみることです。
たとえば、「会議では全員が一度は発言する」「フィードバックは翌日以内に伝える」など、曖昧になりがちな行動ルールを明文化することで、無用なすれ違いや遠慮が減ります。
ポイントは、ルールをトップダウンで決めないこと。メンバー全員が意見を出し合いながらつくることで、納得感と参加意識が高まります。
さらに、ルールは一度決めて終わりではなく、定期的に見直すことで「今のチームに合った状態」を保つことができます。小さなルールの見直しをきっかけに、対話が増え、チームのつながりも強まっていきます。
フィードバック文化の育成
フィードバックは、タイミングや伝え方によって、相手に安心感を与えることもあれば、逆に委縮させてしまうこともあります。だからこそ、「伝え方」だけでなく、「伝え合うこと自体が自然である」という雰囲気をつくることが大切です。
まずは、ポジティブなフィードバックを惜しまず伝えることから始めましょう。「助かったよ」「そこ、よく気づいたね」などのひと言が、日々のやりがいにつながります。
もちろん、改善点について伝えることも必要ですが、その際には「どうすればよくなるか」に視点を置くことが肝心です。批判ではなく提案として伝える姿勢が、相手の前向きな受け止めにつながります。
また、フィードバックは一方通行でなく、双方向であることも忘れてはいけません。たとえば、「このフィードバック、どう感じた?」と問いかけることで、相手の視点を尊重し、信頼を深めるきっかけになります。
こうしたやり取りが日常化すれば、チーム内での率直な意見交換が当たり前の文化として根づきます。結果として、心理的な安心感が高まり、従業員が自らの意見や提案に自信を持てるようになります。
まとめ:心理的安全性が、エンゲージメントの起点になる
職場で「安心して話せる」「失敗を責められない」という感覚を持てるかどうか。それは、従業員がどれだけ仕事に向き合えるか、チームの中でどれだけ力を発揮できるかを大きく左右します。
心理的安全性は、単なる雰囲気や関係性の問題ではなく、エンゲージメント――すなわち仕事や組織に対する自発的な関与や貢献意欲を引き出す土台となるものです。
今回のブログでは、心理的安全性を高めるための具体的な工夫や、実践企業であるトヨタの事例を紹介しました。特別な制度がなくても、1on1の質を見直したり、チームでルールを共有したり、フィードバックの文化を育てたりと、現場でできる取り組みは少なくありません。こうした小さな積み重ねが、やがて職場全体の信頼関係や安心感を育て、従業員の主体性や創造性を引き出していきます。
「心理的安全性を育むことは、組織の未来を育てること」と言い換えてもいいかもしれません。誰もが自分らしく声を出せる環境が整えば、従業員は仕事に意味を見出し、組織とのつながりを実感するようになります。その結果、個人と組織の双方が成長し合える関係が築かれていくのです。
まずは、自分のチームや職場の空気に目を向けてみてください。少しずつでも心理的安全性の土壌を育てていくことが、エンゲージメントを高め、持続可能な職場づくりにつながっていく第一歩になります