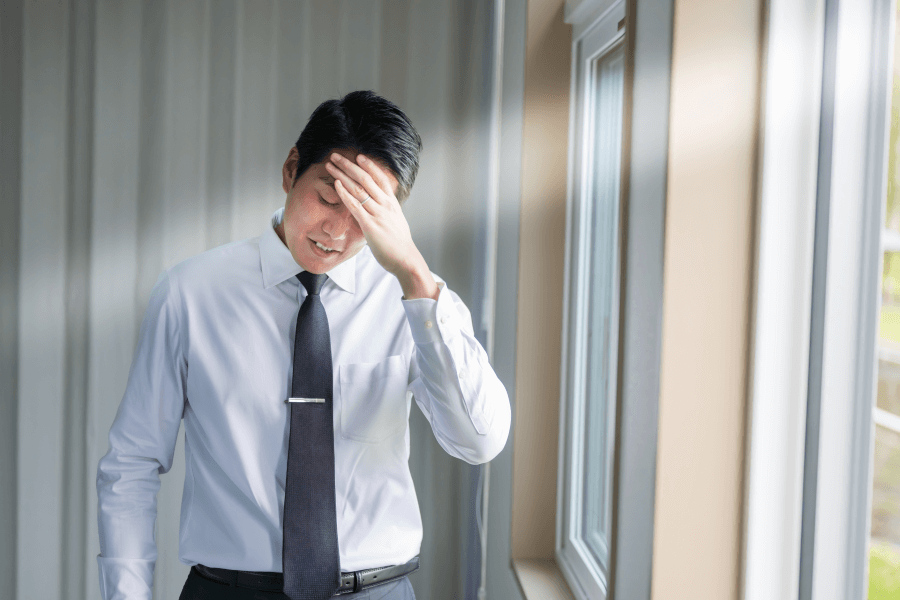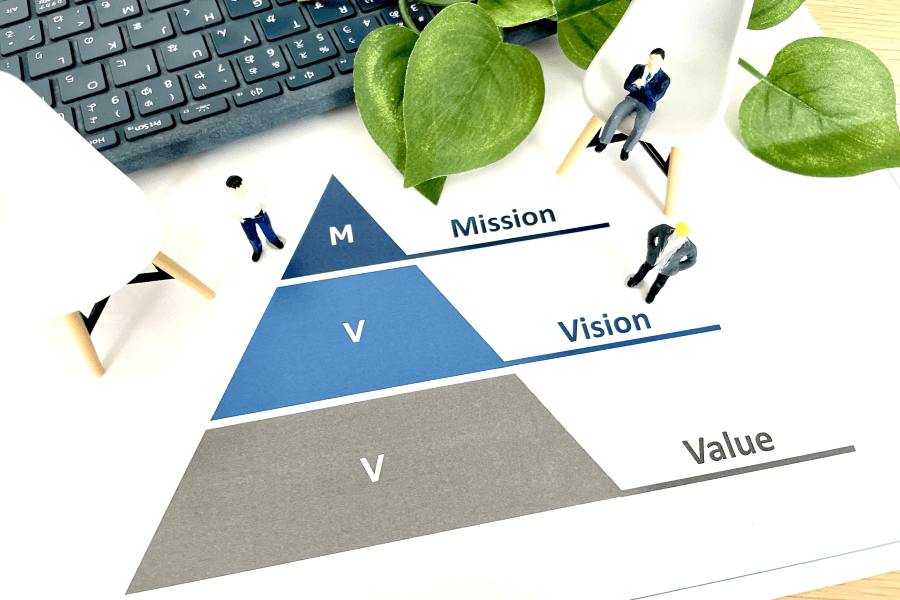マネジメント
【組織を変える】部下フィードバックのおすすめ術
皆さんは“フィードバック”と言われて、どんな行動を想像するでしょうか?
改善点を伝える行為や、もしかしたら叱ったり、注意の言葉を投げかけたりすることがフィードバックだと考える方も多いかもしれません。フィードバックの手法は奥深く、どちらかと言えば、人事の方に必要な手法というよりは、現場のマネジャー・上司(評価者)と部下(被評価者)の間で適切に行われることによって、人材のリテンションの向上や活躍につながっていくものとされています。
本記事は、これをお読みいただいた人事や上司の方が、正しくフィードバックのあり方を理解することで、人材や組織の活性化につなげることができればと思います。
Contents
フィードバックとは
フィードバックには、主にポジティブ・ネガティブという2つの方向性があります。 相手や状況によって使い分けが必要になってくるので、それぞれの効果や注意点について紹介していきます。
ポジティブ・フィードバック
ポジティブフィードバックとは、部下の行動・存在・結果を「承認」することが主眼となる方法です。上司側としては、「まずは相手の努力を褒めてあげたい」「相手に自信をつけさせたい」という狙いでフィードバックを行っていきます。国際エグゼクティブコーチヴィランティ牧野祝子さんの『国際エグゼクティブコーチが教える人、組織が劇的に変わるポジティブフィードバック(あさ出版)』によれば、相手の可能性を信じて、フィードバックを受ける側が「大切に思われている」と素直に感じてもらえることが大事だと言われています。
ポジティブな内容のフィードバックがしっかり行われていると、部下の中での仕事に対する幸福感やモチベーションのUPにもつながっていき、やりがいが生まれていくという好循環のサイクルになっていきます。
しかし、私はこのポジティブなフィードバック(=ポジティブに褒める点を発見する)というのは、「言うは易く行うは難し」だと考えています。上司=昇進しているというのは、いわば「その会社での、その道のプロ」です。故に基本的に、自分よりできない部下の問題点ばかりを見がちです(というよりも、どうしてもそこが目につきやすいというイメージでしょうか)。
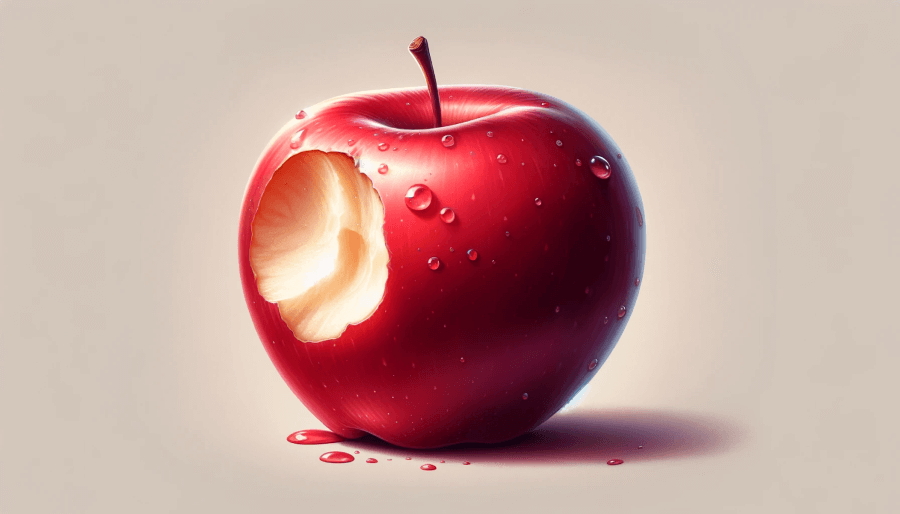
前職リクルートの時に私も良く注意されていたのですが、「上司は、りんごの欠けた部分についつい目が行ってしまう」のです。残っている実の部分を見ると、まだ美味しそう、つまり良いところがたくさんあるのです。そもそも、意図せずとも、上司の視点で見たときに、部下は悪いところのほうが目立ってしまいやすいということを理解しておきましょう!
ネガティブ・フィードバック
ネガティブフィードバックとは、相手の行動の問題や改善すべき点を指摘することで、成長を促していくフィードバックの方法です。株式会社コンカー代表取締役社長三村真宗さんの『みんなのフィードバック大全』では“ギャップ・フィードバック”という言葉が使われています。
「改めて欲しい言動があった」というケースや、「今よりも高いパフォーマンスでの仕事を期待したい」「必要なスキル・スタンスを身に付けてもらいたい」といった場合に使われます。
ネガティブ・フィードバック(ギャップ・フィードバック)が適切に行われると、部下は自ら改善点を模索するようになるため、成長のきっかけに繋がっていきます。一方、過度プレッシャーやストレスを与えてしまう可能性もあるため、言葉遣いなどには十分に配慮する必要があります。軽めと重めなネガティブ・フィードバックがあるということを理解しておきましょう。
フィードバックの分類
前章の概念的な説明を踏まえ、ここでは手法(HOW)の情報を提供していきます。
ポジティブ・フィードバックにおける4つの承認
ポジティブフィードバックにおける承認には、
- ・結果承認
- ・行為承認
- ・存在承認
- ・可能性承認
の4種類があります。
結果承認とは「今回の営業活動での新規案件の獲得は君のおかげだよ!資料もとてもわかりやすかったね」というように、期待していた“結果”に対する前向きなフィードバックを指します。成功体験として認識させ、部下との絆を強くする他、褒められた結果を2回目3回目・・・と生み出していこうという意識が部下の中に生まれていきます。
行為承認は、結果にかかわらず日々の業務やプロセスに対して行うフィードバックを指します。結果が出る前の段階で承認されると、相手は「これでいいんだ」と自信を持つことができ、それが結果につながる後押しになります。前提として、結果が出るのには基本的に時間がかかります。フルマラソンでも給水場があり、水を補給しないと脱水症状を起こす可能性が高いのと同様に、結果というゴールまで走り切るためには、水を補給してあげる必要があります。そんなイメージでプロセスに対して行為承認してあげることも大事なのです。
存在承認は、部下への尊敬を示す最も基本的な承認だと言われています。例えば、「おはよう!」と笑顔でちゃんと顔を見て挨拶をする。これだけのことでも、メンバーが上司に話しかけやすかったり、意見の言いやすい職場環境を作っていきます。笑顔やアイコンタクトもパフォーマンスを変えていくきっかけに繋がっていくはずです。
可能性承認は、将来の可能性を信じて期待し、肯定的に応援することや改善ポイントを伝えることを指します。つまり、ネガティブ/ギャップフィードバックを指します。
ちなみに・・・「承認」には即効性があり、それだけでとても職場の雰囲気が変わると考えています。「チームの状態や雰囲気は上司の内面が反映されたもの」とも言われておりますが、上司が十分な承認で接すれば、それは部下達に伝わり、良好な風土に変わっていくはずです。ストレートかつ相手の顔を見て、「いいねぇ」「なるほどね!」「面白いね!」「嬉しいな」などから始めていくと良いのではないでしょうか?
ネガティブ・フィードバックにおける6つのRight
ここでも前章にご紹介した『みんなのフィードバック大全』を参考に記載させていただいています。こちらの書籍では、ネガティブ・フィードバック(ギャップ・フィードバック)における「6つのRight」というフレームが紹介されています。
1つ目のRightは「Right Occasion(適切な機会に)」です。要は、部下が気持ち新たに「成長したい!」と思っているタイミングで「もっとこうなっていたら良かったかもね!」とネガティブフィードバックをすると効果抜群ですよ、ってことです(笑)。例えば3ヶ月に1回の役員の前での発表機会など、大きな出来事の直後には、誰しも「もっとうまくやる方法があれば知りたいです!」と感じるものだと思います。そのタイミングでポジティブフィードバックと併せてギャップフィードバックを行うと、相手に受け入れられやすいと言われています。
立教大学の中原淳教授も著書『耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術 フィードバック入門』にて、フィードバックをする“機会”や“タイミング”の重要性を説いています。加齢により自己の正当化度合いが高まることは想像がつきやすいかもしれませんが、仕事や役割を長期間担当していると、なかなかフィードバックが伝わりにくくなると言われています。
そこで、中原教授は仕事における役割が変わったタイミング(人材開発用語でいうところの「トランジション」期間)で伝達することが大事である、と述べています。トランジションの直後、部下は精神的に不安定なため、外からのアドバイスが伝わりやすいということです。
このように、先の例のような役員の前での発表という大仕事の後や、トランジション期など、部下が心理的に不安だったり、改善をしたい!と思っているタイミングで、アプローチをすることが大事なのです。
2つ目のRightは「Right Environment(適切な環境で)」です。ネガティブフィードバックの鉄則は「1対1かつ口頭」で行うことです。昨今DXの波に乗り、ZOOMやSlackといったコミュニケーションツールが数多くでてきておりますが、こういったツールは部下の生々しいリアクション(表情はうつむいてるのか、声のトーンが下がってきているのか等)が見れません。つまり言い過ぎてしまうことにつながりやすいのです。加えて、周りの人達がいる環境でのフィードバックもお薦めはできません。
部下視点で言えば、周りの同僚に見られながら、自分の至らない部分を指摘されても、変なプライドが邪魔をし、正しく上司の言葉を受け入れられない可能性があります。また、上司視点で言えば、伝え方によっては部下をみんなの前で晒し者にしているようにも見えるので、得策とは言えません。
3つ目のRightは「Right Tone(適切なトーンで)」です。これは当たり前のことなのですが、あくまで“叱る”のと“ネガティブな内容やギャップのある内容をフィードバックする”のは行為が圧倒的に違います。そのため、感情的になることなく、温かいトーンで、敬意を払いつつ伝えていくことが大事です。
4つ目のRightは「Right Atmosphere(適切な雰囲気で)」です。みなさんは、ある日突然上司から、ネガティブなフィードバックをされると軽めのものであっても面食らうことがありませんか?上司側は軽く伝えたつもりなのに、部下は重たく捉えてしまうという状態です。そういった状態を作らないためにも、普段からポジティブ:ネガティブ=9:1の割合でフィードバックを伝えておくことが大事です。
評価フィードバックや半年に1回の人材開発面談などのイベントでのみフィードバックをしていると、上記のような状態が生まれやすいです。普段のコミュニケーションからフィードバック癖を身につけるようにしましょう!
5つ目のRightは「Right Relationship(適切な関係性で)」です。ネガティブフィードバックが、部下にとって有意義な機会になるかどうかは、部下との関係性に左右されます。「●●さんから言われたくないです!」と捉えられることのないように、日頃の信頼関係を築くことが大事です。
6つ目のRightは「Right Motivation(適切な動機で)」です。あまりないかもしれませんが、フィードバックの中に苛立ち等が混じっていたり、気に入らない部下に対しての感情が混じってはいけません。フィードバックは、常に部下の成長を願う気持ち→その先の組織をもっと良くしていこうと考える気持ちによるものでなければならないのです。
ポジティブとネガティブフィードバックの割合
ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックの割合は、2.9:1が適切な割合だと言われているそうです。この「2.9:1」の割合は、一般的に“ロサダ比”と言われているのをご存知でしょうか?
ロサダ比は、心理学者のバーバラ・フレデリクソン博士とマーシャル・ロサダ氏が2005年に論文で発表した法則で、チームにおいてプラスの感情とネガティブな感情の比率が2.9:1以上の時にチームメンバーの精神状態が充実することが発表されています。「1つ叱って3つ褒める」というフレーズもロサダ比から出てきている言葉です。 ちなみにロサダ比は厳密には「2.9013:1」と論文で示されていますが、さすがにややこしく、簡略化して「2.9:1」や「3:1」と表されています(笑)。なんとなく、パワハラやブラック企業という言葉が流行し始めてから、「ポジティブな内容を部下に伝える割合が多いほうが良いのだろう」ということは認知がされていたと思いますが、学術的に定量で表されているのが、非常にわかりやすいですよね。
具体的なフィードバック手法
事前準備
フィードバックの質を左右するのは実は場数です。そういう意味では実践に次ぐ実践で質を上げていくことが大事ですが、予行練習を通じた、【模擬実践】などを行うことも質を上げる1つの手段になります。特に、フィードバックはネガティブな内容をする場合、受け手が素直に聞き入れてくれない場合もあるので、ついついカッとなってしまうこともあると思います。そのために「脳内予行演習」を行うことをおすすめします。
部下の問題点をどのようなロジックで伝えるか、事前に作戦を立てて発表を想定し練習することで、フィードバック者も緊張したりせずに、伝えたいことを100%部下に伝えきることが可能です。
そして、その事前準備のロジックを組むうえでは、『フィードバックのSBIモデル』というものを用いることが有効です。SBIモデルとは、Situation、Behavior、Impact(状況、行動、影響)をの頭文字を取ってつけられた名前で、状況(Situation)を正確に捉え、観察された部下の特定の行動(Behavior)を把握し、当事者の行動が周囲に与えた影響(Impact)を整理・説明するためのモデルです。
ポジティブだろうがネガティブだろうが、ただただ、「ここが良いね!」「ここが悪いね!」だと、ただの感想です。なんのシーンや、どんな部下の行動をほめたり、直してほしいと思っているのか?正しく伝わるように、事前準備を怠らないようにしましょう!
フィードバックのコツ
フィードバックの際、マネジャーや上司は1つだけ意識しておくべきことがあります。それは、“目的”です。フィードバックも手段であり、フィードバックすること自体が目的ではありません。部下の良い行動をフィードバックすることで、部下のどんなアクションを何度も行ってほしいのか?逆に、部下のどんな改善すべき行動を、しっかりと改善アクションをしてもらうために、フィードバックをするのか?
どんな内容であれ、その先に取ってほしいアクションがあるからこそ、フィードバックをするはずです。そのために、必ず目的を忘れず、且つ、打ち手や取ってほしい具体的なアクションを伝えるようにしましょう。
例えば、「●●のナレッジ展開、皆非常に参考になったって言ってたよ!先程から面談してて、1人1人、そのナレッジのお陰でお客様から契約もらえたって言ってたんだよね。次回もまた余裕ある時お願いできるかな?」と再現して欲しいアクションを伝えたり、逆にネガティブな場面では「先程の上司の場での戦略を発表した際、◎◎部分に関する根拠が少し弱かったかもしれない。それを●●も自覚してて、発表の際にはっきりと主張を伝えられていなかったね。次回は、①上司特に関心があったり、決議に必要としている情報はなにか?②仮に受け手の視点が厳しかったとしても、自身の主張をしっかりと伝えきる、ということを意識しよう!」のように、具体的なアクションまでセットで伝えることが大事です。
目的は、部下を育て、組織を良くすること。そのために、部下にやってほしい行動を具体的に伝え、認識の齟齬が起きないようにしましょう。
【こぼれ話】フィードバックを妨げる日本文化
ちなみに、日本人はフィードバックが苦手とされています。これはハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化による違いが大きいとされています。
ハイコンテクスト文化とは、「コミュニケーションの多くが文脈や暗黙の了解に依存する文化」を指します。言葉にしなくても相手に意図が伝わりやすい環境です。
例えば・・・
・非言語コミュニケーション(ジェスチャー、表情、沈黙など)が重視される。
・共通のバックグラウンドや価値観があるため、言葉を省略しても意図が伝わる。
・礼儀や尊重が重要で、ストレートな表現を避ける傾向がある。
などで、日本、中国、韓国などのアジア諸国やアラブ諸国に多く見られるといいます。
逆にローコンテクスト文化とは「コミュニケーションが言語情報に大きく依存する文化」を指しています。そのため、言葉を明確に使って意図を伝える必要がある環境です。
例えば・・・
・言葉が主な情報源であり、何を言うかが非常に重要。
・異なるバックグラウンドや価値観を持つ人々が多いため、誤解を避けるために詳細で明確な表現が必要。
・率直で直接的なコミュニケーションが好まれる。
などで、アメリカ、ドイツ、スイスなどの西洋諸国などに見られる文化です。
日本はハイコンテクスト文化、つまりコミュニケーションが文脈や暗黙の了解に依存しやすい文化です。また、相手からの見え方を気にしてしまったり、逆に、相手を傷つけないか?を気にしやすかったりします。そのため、日本人はフィードバックが苦手なのです。
そう考えると、文化的にも、我々が苦手なことを自覚化し、練習する価値アリなのが、“フィードバック”という技術です。みなさんも正しいフィードバックを扱えるようになり、部下や組織を改善する手法を身に着けて頂けたらと思います。
さいごに
こういったフィードバックや、また広く言うとコーチングでは最近、“コーチャビリティ”という概念が出てきています。コーチャビリティとは、他者からの助言を聞き入れる能力を指しており、コーチャビリティの高い人は速いペースで成長していきます。
本記事では、マネジャーや上司側のフィードバックスキルを高めることを目的として書いてるので、詳細な説明は避けますが、要は部下側の、話を聞き入れたり、自己成長につなげようとするスタンス形成も大事なのです。
組織にはそれぞれ歴史があります。「前の前の上司はこういう方針だった」「昔の時代はもっと成長できていた」など、過去の組織運営の積み重ねが今の組織なのです。そういう意味ではコーチャビリティというスキルを高めるために、部下に対してのマインドセットを行う発信をしても、過去に思いを馳せて“変わってくれない部下”が一定層出てくることも考えられますよね。
そのような「部下や組織、上司の考え方を抜本的に変えたい!」という段階の際は社外の目や発信をいれるのも1つの手です。組織内の人が話者だと素直に聞き入れられなくても、社外の方からの発信だと、同様の言葉でも、違って受け止められたりすることもあるものです。Tsumuguでは、現場マネジャーや部下のスキルスタンス研修の実施も行っていますので、もしご要望があれば、お問い合わせくださいね。
本日は以上です、ありがとうございました。