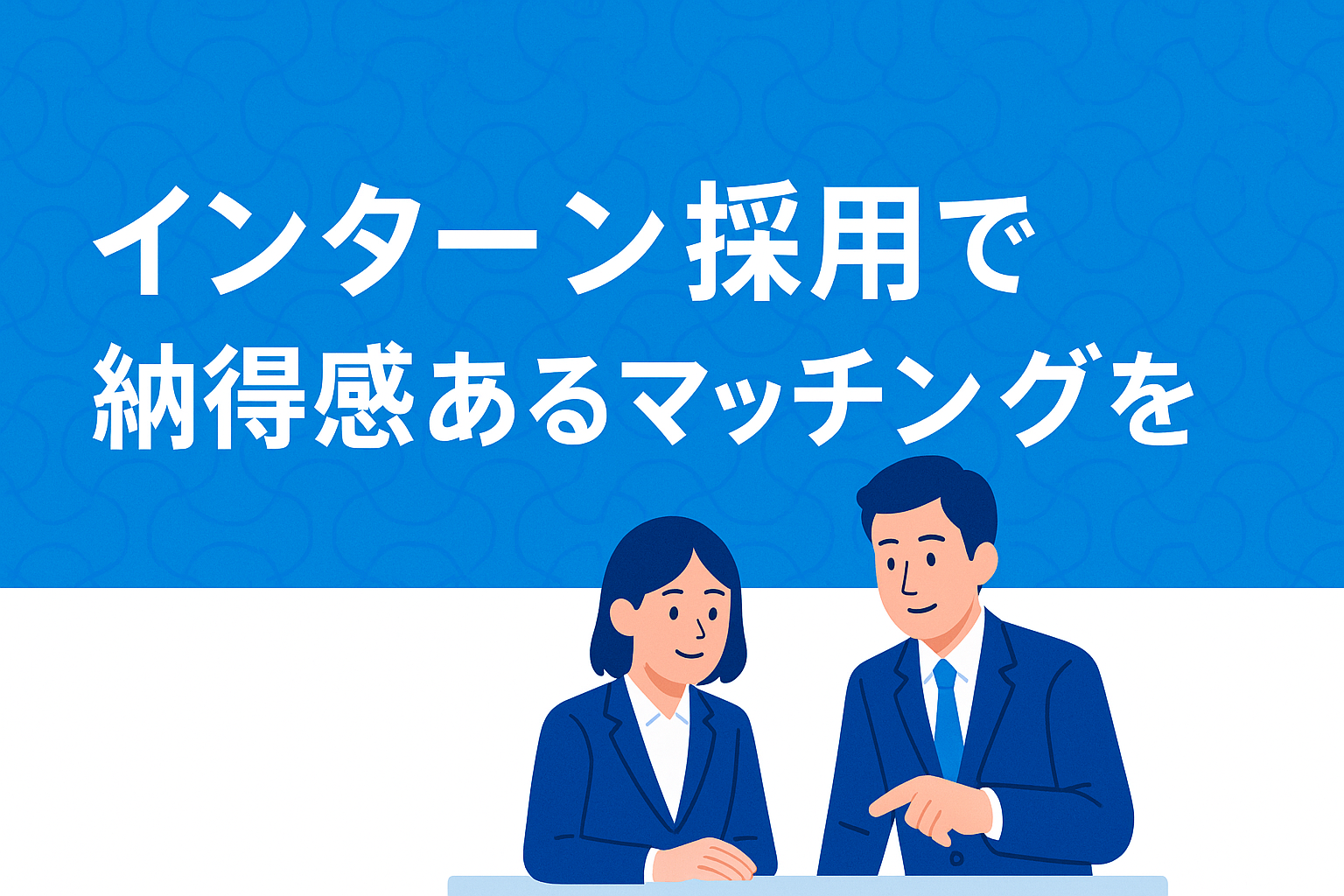更新日
人材採用
採用 競合 調査を自社で行う方法【無料ツール活用】競合との差別化と採用力強化の実践ポイント

採用 競合 調査の方法を知りたい方や、優秀な人材を確保するために自社と競合の違いをどう打ち出すべきか悩んでいる方は少なくありません。特に近年は採用市場の競争が年々激化しており、従来の採用手法だけでは母集団形成や内定承諾率の確保が難しくなってきています。そのため、Google検索やIndeed検索、口コミサイトなど無料で利用できる分析ツールを積極的に活用し、他社の採用動向を把握することが欠かせない取り組みになっています。
求人票の比較や 競合 企業の施策を分析することで、自社の採用活動における強みと弱みを客観的に整理できる点が大きなメリットです。本記事では、誰でも実践できる 競合 調査のステップや、スプレッドシートを使った効率的なデータ管理、さらにBIツールによる戦略の可視化方法まで解説します。これを読むことで、コストを抑えつつ他社と差別化できる採用戦略を構築し、ターゲット人材に響くブランド発信につなげるヒントを得られるでしょう。
Contents
採用 競合 調査を自社で行う重要性
自社で採用 競合 調査を行うことは、 競合 との差別化や採用戦略の改善点を明確にする第一歩です。外部のコンサルティングに依存せず、自社で情報を収集・分析することで、現場に即した具体策を立てられる点が強みとなります。特に中小企業やスタートアップにとっては、限られたリソースの中でも自社の採用力を高める仕組みを内製化できることが大きなメリットです。この仕組みを持つことで、採用活動の再現性が高まり、担当者が変わっても戦略を継続的に運用しやすくなります。
競合 調査が採用戦略に与える影響
競合 調査を行うと、自社の採用戦略そのものに大きな変化と改善のきっかけをもたらします。例えば、競合がどのような待遇や制度を打ち出しているかを把握することで、求職者視点で自社の求人票やメッセージを見直す契機になります。口コミサイトや求人票を比較分析すれば、応募者が重視している要素や不安を感じている部分が浮き彫りになり、改善すべき箇所を的確に把握できます。
さらに、Google検索やIndeedの検索動向を調査することで、最新の採用トレンドや応募者数の推移を把握し、採用計画を柔軟に修正できるようになります。これにより、採用コストの最適化、内定承諾率の向上、そして企業ブランドへの信頼感の強化へとつながります。
他社比較で見えてくる自社の強みと弱み
他社と比較することで、自社が持つ独自の魅力や改善すべき課題を客観的に把握できます。条件面や求人コンテンツを横並びで分析すれば、求職者が「どこに魅力を感じ」「どの部分に不安を持つのか」が明確になります。たとえば、口コミ評価や求人票の細部を精査すると、福利厚生や働き方の柔軟性といった訴求ポイントが浮き彫りになります。
一方で、 競合 と比較して不足している部分も明確になり、改善の優先順位をつけやすくなります。こうしたプロセスを経ることで、差別化ポイントを求人票や採用広報に反映でき、ターゲット人材に響く戦略的な採用活動へとつなげられるのです。
無料で使える採用競合調査の方法
採用競合調査を進めたいと考えていても、限られた予算の中では外部コンサルや有料ツールを導入するのは難しいケースも少なくありません。そうした企業にとって、無料で利用できるツールや方法を組み合わせて情報収集を行うことは、もっとも現実的で効果的なアプローチです。代表的な手段としては、Google検索やIndeed検索に加え、口コミサイトやSNSの活用があります。これらを継続的にモニタリングすることで、競合企業の採用戦略や市場動向を的確に把握し、自社の改善点を見つけやすくなるのです。
Google検索を活用した競合分析
Google検索は、競合企業の採用ページや市場のトレンドを素早く調査できる最も身近な方法です。コストをかけずに情報を収集できるため、採用担当者がまず着手すべき調査手段といえるでしょう。
「採用+職種+地域」での検索テクニック
「採用+職種+地域」といったキーワードを組み合わせて検索することで、同じターゲット人材を狙っている競合の求人情報を効率的に一覧化できます。たとえば「採用 営業 東京」と検索すれば、同一条件で募集している企業の求人票や採用ページが表示され、条件や待遇を横並びで比較可能です。さらに検索結果から、新卒採用市場の動向や採用トレンドを読み取ることもでき、応募者数推移などの参考情報を得やすくなります。この手法を定期的に実施することで、採用戦略の立案や差別化ポイントの発見に直結します。
競合企業の採用ページ・プレスリリースを調べる
競合企業の採用ページやプレスリリースを確認すると、最新の採用戦略や求人コンテンツの強調点を把握できるため、自社の改善に役立ちます。給与や勤務条件、独自の福利厚生制度などは競合が差別化の武器として提示することが多く、比較対象として有益です。また、プレスリリースには新制度の導入や採用人数の推移といった情報が盛り込まれる場合があり、採用競争力を強化するための根拠ある分析が可能となります。こうした情報をスプレッドシートに整理することで、強み・弱みを体系的に可視化し、戦略的な改善策を検討しやすくなるのです。
Indeedでの求人票比較と応募動向の把握
Indeedは、求人票の比較や応募数推移を無料で確認できる有効なツールです。競合の募集状況や採用トレンドを把握し、自社求人を改善するヒントを得やすい点が大きな強みです。
募集条件・待遇を横並びでチェック
Indeedで同じ職種や地域に絞り込んで検索すれば、給与・福利厚生・勤務時間などを横並びで比較できます。これにより、自社求人に不足している要素や逆に強調すべき部分が明確になります。スプレッドシートで条件を項目ごとに整理することで、差別化ポイントを体系的に把握し、採用コンテンツに的確に反映できます。応募者は待遇だけでなく、企業ブランドや職場の雰囲気にも注目するため、比較分析を通じた強みの発信が欠かせません。
応募数推移や求人掲載順位の確認方法
Indeed内では、求人の掲載順位や応募数推移も確認可能です。掲載順位は検索結果での表示位置を意味し、上位に表示されるほど応募者の目に触れやすくなります。加えて、過去1〜3か月の応募数推移を追跡すれば、採用施策の効果や最適な実施タイミングを見極められるでしょう。これらをスプレッドシートで記録しておけば、経営層への報告資料としても活用でき、根拠ある戦略判断が可能になります。
口コミサイトやSNSでの評判調査
求人票や採用ページでは伝わらない、応募者が実際に感じる企業イメージを把握するには口コミサイトやSNSが有効です。特にブランドロイヤリティや働きやすさに関する評価は、ターゲット人材の応募意欲に大きく影響します。
応募者が参考にする企業口コミの見方
多くの応募者は、転職口コミサイトや就活掲示板を利用して、職場環境やキャリアパス、福利厚生といった情報を事前に確認しています。競合企業の口コミも確認すれば、応募者が何を重視しているかを知ることができ、自社の改善にもつながります。口コミを「雰囲気」「キャリア」「待遇」などの切り口で分類・整理することで、改善点や訴求ポイントを客観的に把握できるのです。
ブランドロイヤリティや職場イメージを探る
SNSや口コミから「成長機会」「働きやすさ」「職場の温かさ」といった評価が多く寄せられている企業は、応募者の間で高い信頼やロイヤリティを築きやすい傾向があります。自社と他社を比較することで、強化すべき要素や改善すべき課題が明確になり、採用戦略を磨き上げる指針となります。収集した情報を求人票比較やスプレッドシートに整理し、応募者に響くコンテンツへ反映していくことが重要です。
※他にもデータを活用した採用に関する記事がございます。是非こちらもご覧ください。
採用競合調査を効率化する無料ツール
採用競合調査を効率的に行うためには、スプレッドシートや無料で使えるBIツールの活用が効果的です。こうしたツールを取り入れることで、データ整理や可視化が容易になり、分析の精度が向上します。特に、中小企業や限られたリソースで採用活動を行う企業にとって、無料ツールを組み合わせることは、コストを抑えながら競合分析を高度化できる実践的な方法といえます。
スプレッドシートを使ったデータ整理・分析
スプレッドシートを利用すれば、求人票の比較や応募数の推移といった情報を一覧化して管理でき、差別化ポイントを客観的に抽出しやすくなるのが特徴です。自社と競合を並べて可視化することで、採用戦略の見直しがスムーズに進みます。
求人票の項目比較テンプレート
求人票の条件を比較する際には、スプレッドシートで項目別に整理できるテンプレートを作成するのが有効です。具体的な項目には「給与」「勤務形態」「福利厚生」「勤務地」「応募資格」「仕事内容」などが挙げられます。各項目に競合ごとの特徴を書き込めば、強み・弱みが明確になります。たとえば、「競合Aは新卒向けインターン制度が充実」「競合Bは柔軟な勤務形態が人気」といった情報を並べることで、自社の改善策や訴求ポイントを整理しやすくなるのです。このテンプレートは、採用担当者だけでなく、経営層への報告資料や求人票改善の根拠としても役立ちます。
条件・待遇の一覧化で差別化ポイントを可視化
求人票の条件や待遇を一覧化することで、競合との違いや自社の強みが一目で確認できる形に整理されます。たとえば「給与」「特別休暇」「資格取得支援」といった要素を表にまとめて比較すれば、採用市場における自社のポジションが明確になります。これにより、求職者の応募動機に直結するポイントを見つけ出し、ブランドロイヤリティを高めるための施策につなげることができます。定期的にこの一覧化を行えば、短期的な改善だけでなく、中長期的な採用ブランディング強化にもつながります。
無料BIツールでのデータ可視化
スプレッドシートで整理したデータをさらに深掘りするには、無料のBIツールを使ってグラフやチャートで可視化することが効果的です。数値を図表化することで、経営層への説明が分かりやすくなり、戦略立案の根拠としても説得力が増します。
採用トレンドをグラフ化して経営層に報告
無料BIツールで応募者数や求人掲載順位の推移をグラフ化すれば、採用市場の動きを直感的に把握できる資料を作成できます。例えば時系列で応募数を追跡すれば、どの時期に競合が強いか、どの施策が効果的だったかを一目で確認可能です。差別化ポイントや強み・弱みを図表で提示することで、経営層が迅速かつ戦略的に判断できる環境が整います。
自社と競合の採用活動を定量的に比較
また、BIツールやスプレッドシートで「応募者数の推移」「求人掲載順位」「採用率」といったデータを整理すると、自社と競合の採用活動を定量的に比較できるようになります。これにより、競合調査の精度が高まり、改善点がより具体的に見えるようになります。さらに、こうした定量データを蓄積することで、長期的に自社が勝ちやすい採用パターンを発見する手掛かりにもなります。結果として、採用戦略全体を根拠ある形で最適化でき、ブランド強化や人材獲得の成功率向上にもつながります。
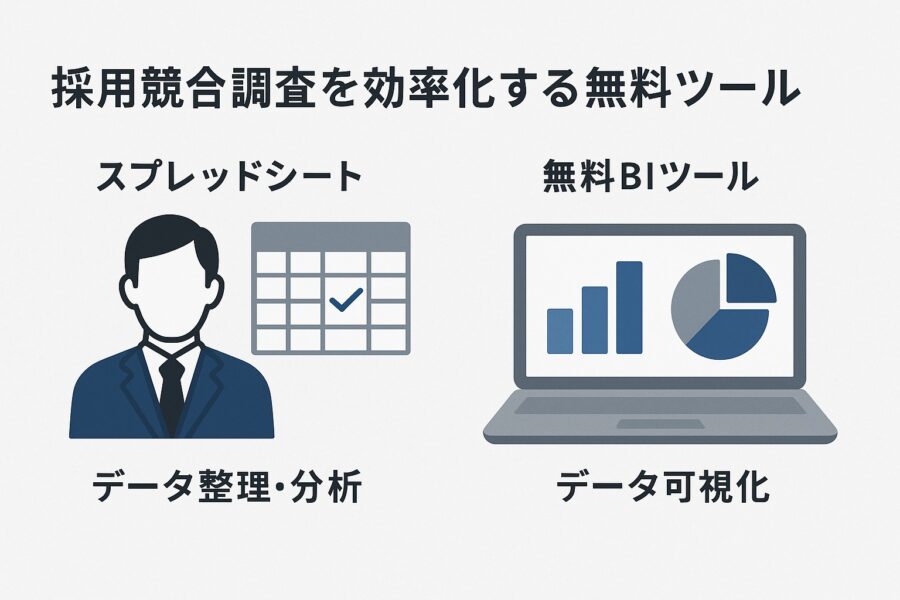
成功企業に学ぶ!採用競合調査の活用事例
採用競合調査は理論だけでなく、実際に成果を出している企業の事例を参考にすることで、自社の採用活動に直結する改善点を見つけやすくなります。他社の成功パターンを学ぶことは、自社の強みや差別化ポイントを客観的に発見する近道です。ここでは、実在する企業の取り組みを紹介しながら、採用競合調査をどう活用できるかを見ていきます。
サイバーエージェント|学生人気企業の採用競合分析
サイバーエージェントは、就活口コミサイトやSNSに投稿された学生の声を徹底的に収集・分析しています。そこで得られた情報をスプレッドシートに整理し、エントリーしてくる学生の傾向を分類。さらに他の人気企業との比較を行い、どの要素が差別化に直結しているかを定量的に可視化しています。
たとえば、「カルチャーを重視する学生層が厚い」「成長機会の豊富さが魅力」「働きやすさが応募意欲につながる」といった評価が企業ブランドの強みであることを突き止め、それらを求人コンテンツや採用広報に積極的に反映しました。このサイクルを継続的に回すことで、母集団形成を安定させ、新卒採用市場でも長年にわたり高い人気を維持しています。
リクルート|求人票比較を活用した条件設計
リクルートは、Indeedや自社の求人媒体をもとに、競合企業の待遇や条件を定期的に調査・比較しています。職種ごとに応募率や相場感をスプレッドシートに一覧化することで、市場の動きをリアルタイムに把握しやすくしているのです。
さらに、求人票比較のテンプレートを活用して他社と自社の条件を並べることで、どの待遇が強みで、どこに改善の余地があるかを明確化。その結果を反映し、応募率を高めるための条件設計に取り組んでいます。この取り組みは単なる比較にとどまらず、競合との差別化ポイントを可視化し、優秀な人材を獲得するための実践的な戦略となっています。
Sansan|データドリブン採用戦略
Sansanでは、ATS(採用管理システム)や候補者データに加え、外部サーベイなどの情報を組み合わせた分析によって、給与水準の競争力や採用オペレーションの改善点を定量的に把握しています。結果として特定職種の給与改定が内定承諾率の向上に直結した例もあります
さらに、「狩猟型採用」から「農耕型採用」へとシフトし、タレントプールを活用した中長期の採用マーケティングを実践。応募しなかった方や辞退した方も含め継続的に関係を築き、転職関心が高まったタイミングでアプローチできる仕組みを作っています。
また、採用活動に必要なデータ基盤を自ら整備し、応募数や通過率などの指標を可視化した上で、採用プロセスのPDCAを回す体制を構築しています。
採用競合調査から導く自社の戦略
採用競合調査で得られたデータは、単なる比較材料ではなく、自社の採用活動戦略を明確にする指針となります。現状を客観的に把握するとともに、他社との差別化ポイントを発見できれば、それ自体が強力な武器となります。継続的に調査を行うことで、自社の採用活動を改善するサイクルを確立でき、長期的な採用力の強化につながります。
応募者視点での比較から改善点を見つける
採用競合調査で重要なのは、応募者視点に立って自社と競合を比較することです。口コミサイトやSNSに寄せられた声を分析し、「企業文化」「成長支援」「職場環境」などの評価項目をスプレッドシートで整理することで、求職者が何を魅力と感じ、どこに不安を抱いているかを明確にできます。
さらに応募者数推移や待遇条件といった定量データを組み合わせて分析すれば、自社の採用活動を客観的に評価可能です。そこから導き出した改善点を求人票や採用ページに反映することで、応募者にとってより魅力的な企業像を示すことができます。結果として、ターゲット人材が共感しやすい差別化ポイントを強化できるのです。
差別化ポイントを求人コンテンツに反映する
競合調査を通じて見つかった差別化要素は、求人コンテンツへ具体的に落とし込むことが必須です。例えば「独自の研修制度」「柔軟な勤務体制」「ワークライフバランスの強化」といった特徴は、求人票や採用ページで丁寧に説明することで、応募者の関心を引きやすくなります。
また、競合比較によって得られた強み・弱みの分析結果は、単に内部で共有するだけでなく、採用戦略の訴求材料として積極的に発信することが重要です。こうした工夫は、企業ブランドロイヤリティの向上や応募者数の増加につながり、効率的に優秀な人材を獲得する基盤を築くことができます。
長期的な採用ブランド強化につなげる
採用競合調査は一度きりの施策ではなく、定期的に実施してデータを蓄積することで真価を発揮します。継続的な他社比較を行えば、自社の魅力や改善点をより正確に把握でき、採用広報や求人コンテンツの質を高めることが可能です。
さらに、無料分析ツールやスプレッドシートで蓄積したデータを活用し、採用トレンドの変化や競合状況を経営層へ定量的に報告すれば、経営判断の根拠としても機能します。こうした取り組みの積み重ねが、採用市場における競争力の維持と、優秀人材の持続的な確保につながります。
まとめ:採用競合調査で効果的に人材獲得を進めよう
採用市場の競争が激化する今、競合調査は単なる比較作業ではなく、自社の採用力を高めるための重要な戦略プロセスです。Google検索やIndeed、口コミサイトといった無料ツールを活用し、求人票や評判を整理・分析することで、応募者が何を重視し、どこに不安を抱いているのかを客観的に把握できます。さらに、スプレッドシートやBIツールで情報を体系的に可視化すれば、現場担当者の改善施策だけでなく、経営層への説得力ある提案や中長期的な戦略立案にも直結します。
特に、自社で調査を継続的に実施することが大きな意味を持ちます。一度きりの調査ではなく、定期的に競合の動向や市場の変化を把握することで、自社の強みや弱みをアップデートし続けることができます。その結果、求人票や採用広報に差別化ポイントを的確に反映でき、ブランド力や応募率の向上にもつながります。
こうした取り組みを積み重ねることで、採用活動における再現性が高まり、担当者が変わっても継続的に成果を出せる仕組みが築かれます。採用競合調査は、優秀な人材を安定的に確保し続けるための土台となる取り組みといえるでしょう。