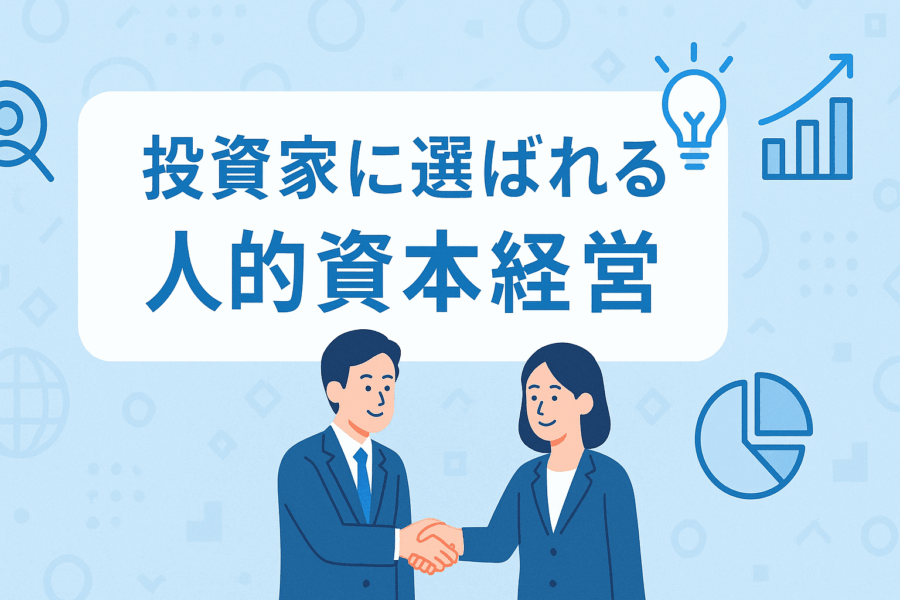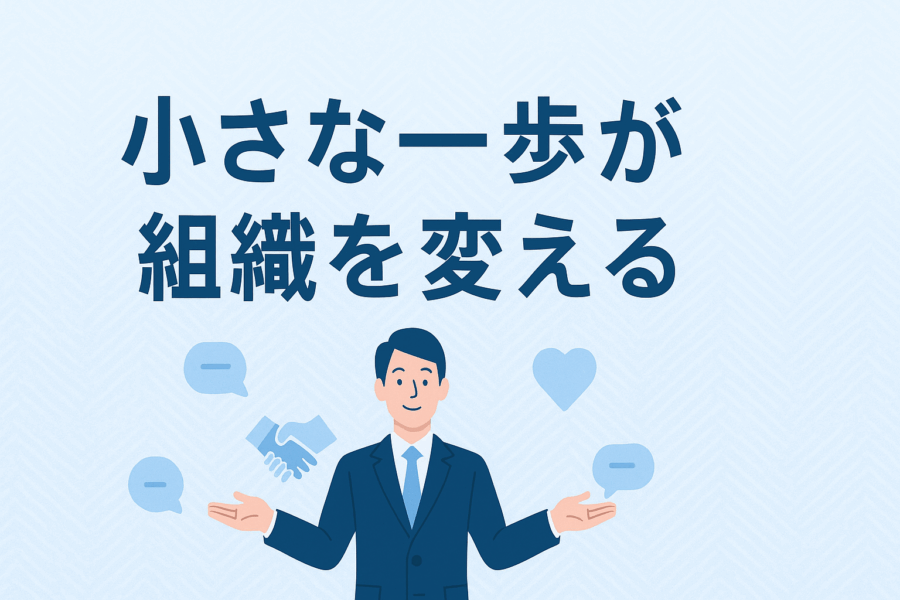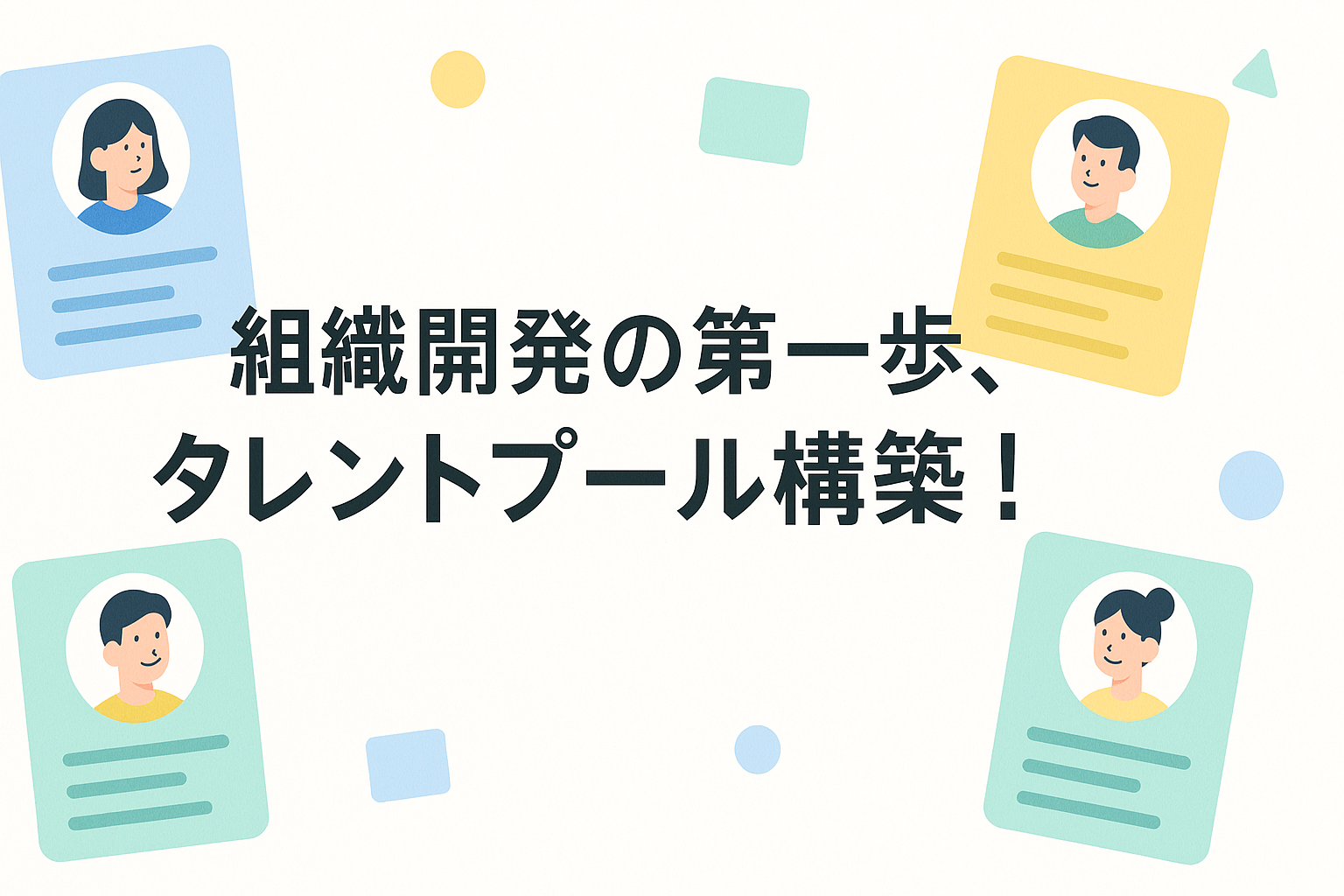更新日
人材活躍
人的資本経営
リスキリング 成功事例の紹介:企業の成長戦略と持続的競争力強化の秘訣

現代は、DXやAIといった技術革新が急速に進み、企業はこれまで以上に「いかに競争力を維持し、さらに高めるか」という課題に直面しています。特に人材育成や社員教育の担当者、そして経営層にとっては、「自社の人材をどう新しい時代に適応させるか」や「 リスキリング によってどのような成果が得られるのか」といった具体的な疑問が尽きません。
本記事では、実際に リスキリング を導入し成果を上げた企業の事例を交えながら、その背景や進め方をわかりやすく整理します。また、KPIやROIなどの数値指標を用いて投資対効果を評価する方法にも触れ、読後には自社で取り組む際の具体的なイメージが持てる内容にしています。企業が成長戦略の一部として リスキリング をどのように位置づけ、実行しているのか、そのヒントを得られる構成です。
Contents
リスキリング とは?今なぜ企業に必要なのか
リスキリングとは、社員が新しいスキルを習得し、企業が市場や技術の変化に迅速に対応できるようにする施策です。近年では、持続的な成長を目指す上で欠かせない取り組みとなっています。
DX・AI時代に求められるスキル構造の変化
DXやAIの導入によって、求められるスキル構造は従来とは大きく変化しています。従来の業務知識に加え、デジタルスキルやデータ分析能力が重視されるようになりました。例えば営業部門では、データに基づく意思決定やデジタルツール活用の重要性が高まり、製造業ではIoTやAIを活用した生産ライン最適化が進展。現場技術者にも新たな知識やプログラミングスキルの習得が求められています。さらに、バックオフィスでもクラウドサービスや自動化ツールの活用が当たり前となり、業務効率化が急務です。こうした変化に応じるため、多くの企業が社内教育やオンライン学習プラットフォームを活用し、スキルギャップの解消に取り組んでいます。
中小企業でも避けられないスキル転換の波
スキル転換は大企業だけの課題ではありません。市場構造の変化や新サービスへの対応が迫られる中、中小企業でも従来の専門性だけでは競争力維持が難しくなっています。地場の製造業では生産管理システムやクラウド活用の能力、小売業やサービス業ではSNS運用やECサイト管理、顧客データ分析などのスキルが不可欠に。予算や人材面で制約のある中小企業でも、助成金や補助金を活用した研修、外部機関との提携、オンライン学習の導入など、低コストで始められる方法が広がっています。こうした取り組みにより、地方や小規模な企業でも事業変革や成長の機会が確実に増えています。
※他にもAIを活用した人材育成に関する記事がございます。是非こちらもご覧ください。
リスキリングを成功させる企業の共通点
リスキリングで成果を上げている企業には、いくつかの共通点があります。「目的とゴールの明確化」、「継続的な学びを支える仕組み作り」、そして「成果を数値で可視化する体制の確立」です。これらをバランス良く実行することで、短期的な成果だけでなく、長期的な人材育成の土台を築くことができます。
目的とゴールを明確化する
リスキリングの取り組みは、方向性が曖昧なままでは効果が半減します。そこで重要なのが、研修や教育プログラムの「目的」と「最終ゴール」を明確にすることです。
例えば、「DX化に伴う新しい業務フローに対応できる人材を育成する」や「AI活用によって業務効率を向上させる」など、経営課題や事業戦略と直結した目標を設定します。さらに、部門ごと・職種ごとに必要なスキルや学習ニーズを洗い出せば、社員自身も自らの成長ビジョンを描きやすくなります。
また、KPI(重要業績評価指標)や具体的な数値目標を組み込むことで、進捗を定期的に確認しながら改善でき、組織全体で目指す方向性を共有できます。こうした明確な目的設定は、リスキリング成功の出発点です。
学びを継続させる仕組み作り
リスキリングは一度で終わらせず、継続して取り組むことが成果につながる活動です。そのためには、学びを日常の中に定着させる仕組みが欠かせません。
例えば、定期的な社内研修やeラーニングの導入、社内外での勉強会開催は有効な手段です。社員が必要なときにすぐアクセスできる学習プラットフォームの整備も重要です。さらに、自主的な学びを促す企業文化を育てるために、ナレッジ共有会や社内SNS、メンター制度などを活用し、社員同士が互いに教え合う機会を増やします。
上司や人事担当者が進捗を定期的にフォローすることで、学習の中断やモチベーション低下を防ぎ、習慣化を後押しできます。こうした仕組みが、持続的なスキル習得を支える基盤になります。
成果を数値で可視化する方法(KPI・ROI)
リスキリングの効果を数字で示すことは、継続的な取り組みを正当化し、社内の理解を得る上で不可欠です。代表的な方法は、事前にKPIやROI(投資対効果)を設定し、定期的に進捗を測定することです。
例えば、新しいツールの習得率、資格取得者数、業務効率の改善によるコスト削減額などは分かりやすい指標です。さらに、研修後に成果を上げた社員の割合や売上への影響も測定対象になります。
これらのデータを月次や四半期ごとにレポート化し全社共有すれば、リスキリングの価値を社内外に明確に示せます。数字に基づく評価は、改善点の特定も早く、迅速な戦略修正や新たな施策立案にもつながります。

成功事例から学ぶリスキリングの手法
実際に成果を上げている企業の事例は、自社の研修内容や人材育成施策を見直す上で非常に参考になります。ここでは、大手から中小企業まで幅広い事例を取り上げ、リスキリングを成功させるためのヒントを探ります。
ダイキン工業株式会社:IoTやAIの社内教育プログラム
ダイキン工業株式会社は、空調機器のグローバル展開とDX推進の一環として、IoTやAIを活用した社内教育プログラムを構築しました。専門教育チームを社内に設置し、現場エンジニアや営業担当者向けにIoT基礎講座やAI応用セミナーなど、多彩な講座を定期的に開催。
特徴的なのは、実務で活用できるデータ分析手法やAIアルゴリズムの基礎をワークショップ形式で学べる点です。受講後すぐに業務へ応用できるため、従業員のデジタルリテラシーは大幅に向上。結果として、IoT製品の開発スピードの加速、生産性の向上、サービス品質の改善につながっています。
さらに、社内学習プラットフォームで受講状況や成果をKPIベースで可視化し、進捗管理を徹底。実務直結型のスキル育成とデジタル教育の融合が、同社のリスキリング成功の大きな要因となっています。
株式会社日立製作所:デジタル人材育成プログラム
株式会社日立製作所は、グローバル市場での競争力を高めるため、全社規模でデジタル人材育成プログラムを展開しています。AI、クラウド、データサイエンスなどの最新技術を、階層別・職種別に最適化した専用講座として提供。
プログラムはeラーニングと集合研修を組み合わせ、さらに実際の業務課題をテーマにしたハンズオン研修も実施しています。受講後は即座に社内プロジェクトへ参加できる体制を整え、学んだスキルを現場で活かせる環境を確保。
研修の効果はKPIや業務成果指標で定量的に評価され、成果を上げた社員は社内でロールモデルとして紹介されます。これにより社員のモチベーションが高まり、DX推進の加速や新規サービスの創出へと直結。日立製作所の事例は、学びと実務の融合が業績向上につながる好例です。
西川コミュニケーションズ:3DCG学習の機会提供
西川コミュニケーションズは、印刷業という伝統的な業界でありながら、3DCGを活用した新たな価値創造に取り組んでいます。社内で3DCGデザインやモデリングの研修を定期開催し、デジタル表現力や最新ソフトの操作スキルを社員に習得させています。
対象は製品企画や営業部門にも広がり、提案力や顧客対応力の向上に直結。さらに、外部のデジタル専門学校やベンダーと提携することで、教材の質や指導体制を強化しています。
この結果、社員は紙媒体だけでなくWeb・映像・VRといった新たな分野のサービス開発に挑戦可能となり、受注案件の増加や若手採用力の向上も実現。西川コミュニケーションズの取り組みは、社外リソース活用と社内教育を両立させた中小企業の成功モデルとして注目されています。
中小企業が実践できるリスキリングのステップ
中小企業がリスキリングを始める際は、現状の正確な把握から無理のない計画づくり、そして低コスト施策や助成金制度を活用した段階的な実施が効果的です。限られた予算や人員でも、着実に成果を上げられる方法があります。
現状分析とスキルギャップの可視化
リスキリングの成果を高めるためには、社内のスキル現状を正しく把握し、必要なスキルとのギャップを明確にすることが出発点です。まず、企業が今後必要とするスキルセットと、社員が現在保有しているスキルを一覧化します。そのうえで、「顧客対応力は高いがデジタルマーケティングの知識が不足している」など、具体的な不足部分を洗い出します。
この際、人事部門や経営層へのヒアリング、社内アンケート、業務KPIの分析など複数の方法を組み合わせることで精度が高まります。スキルシートや人事評価制度の活用、外部コンサルタントによる診断も有効です。こうして可視化した情報をもとに、優先順位を付けた育成分野や研修内容を策定すれば、短期間で効果を実感できる施策に落とし込めます。
低コストで始められる研修・教育方法
中小企業の場合、費用や人材リソースを抑えながら実行できる仕組みが鍵となります。例えば、無料や低価格のオンライン学習プラットフォーム、自治体や商工会議所が主催する公開研修の活用は手軽かつ効果的です。
社内での勉強会や、外部講師を招いた短期セミナーも、費用対効果の高い方法です。さらに、社内の得意分野を持つ社員同士が知識を共有する「ナレッジシェア」活動は、講師費用が不要なうえ、組織内のコミュニケーション活性化にもつながります。資格取得支援や自己啓発費用の補助制度を導入するだけでも、学習意欲を引き出せます。
また、助成金制度と組み合わせることで実質的なコスト負担を大幅に軽減できるため、継続的な教育施策が現実的になります。
補助金・助成金の活用ポイント
限られた予算でも質の高いリスキリングを実現するためには、補助金や助成金の戦略的活用が欠かせません。中小企業向けには、厚生労働省の「人材開発支援助成金」や経済産業省の「IT導入補助金」など、研修や教育プログラムに使える支援制度が多数存在します。
申請の際は、対象となる研修内容・実施期間・期待効果を明確にし、企業の成長戦略と結び付けて記載することが採択率向上のポイントです。受給後は、成果報告や研修参加記録、KPI達成状況の提出、安全衛生管理体制の整備などが求められる場合があります。
申請業務は社外専門家や行政書士に依頼すれば負担を軽減できます。こうした制度を活用することで、予算の制約がある中小企業でも最新スキルの習得や教育環境の整備が可能となり、持続的な競争力強化につながります。
社員のモチベーションを引き出す工夫
社員が主体的に学び続けるためには、評価制度や業務設計、社内文化の工夫が欠かせません。特に、学習そのものを評価に反映し、実務と結び付け、さらに知識を共有する環境を整えることが、継続的なリスキリング推進の鍵となります。
評価制度に学びのプロセスを組み込む
リスキリングの効果を最大限に引き出すには、学習そのものを社員評価の一部として位置づけることが重要です。たとえば、研修や自己学習の参加履歴を人事評価ポイントに加算したり、資格取得やスキル習得を昇給・昇格の条件に組み込む方法があります。
また、進捗報告会や複数部門との連携を通じて、学びに積極的な社員を社内表彰する制度を設ければ、努力が可視化されモチベーションも向上します。PDCAサイクルを活用し、一定期間ごとに学習目標の達成度を確認することで、成長が定量的に把握でき、「やらされ感」を減らして主体性を引き出す効果もあります。こうした制度改革は、社員一人ひとりの成長を正当に評価し、リスキリング推進の好循環を生み出します。
学びを業務成果に直結させるOJTの高度化
OJT(On-the-Job Training)は、研修で得た知識を即実務に活かすための重要な架け橋です。研修内容をすぐ現場業務に反映できるよう、OJTプログラムを再設計し、学びが習熟度や生産性の向上に直結する流れを作ります。
メンターや先輩社員とのペアワーク、課題解決型の共同作業、役割交代やプロジェクト参加などを通じて、実践を重ねながら経験値を高めることがポイントです。さらに、OJTの進捗や指導内容をシートやシステムで管理し、成果や達成度を定量的に評価します。定期的な振り返りやフィードバックを行えば、知識の定着と弱点克服が促進され、研修と実務が一体化した成長環境が整います。
ナレッジ共有文化を根付かせる方法
社内にナレッジ共有の文化が定着すると、社員同士が教え合い、学び合う好循環が生まれます。具体的には、社内SNSやチャットツールなどを活用して、ノウハウや最新情報をタイムリーに発信・共有する場をつくります。
また、週次・月次で勉強会や情報交換会を開催し、実務事例や学習成果の発表機会を増やすことも効果的です。講師役となる社員のローテーションや、知識共有の貢献度を評価する表彰制度を取り入れることで、積極的な参加を促せます。さらに、社外ネットワークへの参加や他社事例の吸収も、視野を広げ成長を加速させます。
こうした文化が根付けば、一人ひとりの能力向上とチーム全体のパフォーマンス強化が同時に進み、リスキリング効果が長期的に持続します。
リスキリング効果を最大化するための組織づくり
リスキリングを単なる研修施策で終わらせず、組織全体の成長戦略として定着させるためには、管理職の意識改革や心理的安全性の確保、社外連携など組織的な仕組みづくりが不可欠です。これらが揃うことで、学びの成果が全社に波及し、持続的な競争力強化につながります。
管理職の意識改革と育成スキル向上
リスキリングの浸透には、管理職の役割が極めて大きいと言えます。管理職が部下の成長を後押しし、学びを尊重する姿勢を持つことで、組織全体に前向きな学習ムードが広がります。
例えば、定期的な1on1ミーティングで部下の学習状況や課題をヒアリングし、個々に合った研修機会やアドバイスを提供することは効果的です。加えて、管理職自身の育成スキルを磨くための外部研修やコーチング、自己研鑽も欠かせません。
さらに、評価制度やKPIに「部下の育成成果」を組み込み、成果に応じて管理職を評価する仕組みを作れば、リスキリング推進が役割の一部として定着します。管理職自身が新しいスキルや手法に挑戦する姿を見せることも、社員の主体的な学びを促す大きな要因となります。
学習を促す心理的安全性の確保
リスキリングの継続には、心理的安全性の高い職場環境が必須です。心理的安全性とは、社員が自分の意見やアイデア、悩みを安心して発言できる状態を指します。
例えば、失敗を恐れずチャレンジできる職場や、学びへの取り組みを肯定的に受け入れる文化があると、社員はより積極的に新しいスキル習得に挑戦します。実践方法としては、傾聴型コミュニケーションの徹底、情報交換や意見発表の場の定期開催、匿名フィードバックやメンター制度の導入などがあります。
また、研修での失敗や試行錯誤を「成長の証」として称賛する文化を根付かせることで、「やらされ感」や不安が減り、創造力と学習意欲が大きく高まります。
社外ネットワークや業界連携の活用
リスキリング効果をさらに高めるには、社外とのつながりを積極的に活用することが有効です。業界団体や同業他社が主催する勉強会、セミナー、ワークショップに参加すれば、最新のトレンドやスキル、成功事例を効率的に吸収できます。
また、教育機関や専門家と提携し、自社では提供が難しい高度な教育コンテンツを取り入れることも可能です。地方自治体や大学との協力により研修機会や人材をシェアすれば、助成金を活用したコスト削減も実現できます。
さらに、業界を越えてベストプラクティスを共有すれば、自社独自の育成モデルを構築しやすくなります。こうした外部連携は、人材育成の幅を広げるだけでなく、組織の競争力を中長期的に強化する重要な戦略となります。
まとめ:未来に向けた競争力強化の鍵は「継続的なリスキリング」
DXやAIの進化が加速する現代において、企業はこれまで以上に変化への柔軟な対応力と持続的な成長戦略を求められています。本記事で紹介したように、目的とゴールの明確化・継続的な学びを支える仕組み・成果を数値で可視化する体制は、リスキリングを成功に導くための三本柱です。これらを確立することで、短期的な効果だけでなく、長期的な人材育成の基盤を築くことができます。
また、ダイキン工業や日立製作所、西川コミュニケーションズの事例が示すように、実務直結型の研修設計や外部ネットワークとの戦略的な連携は、企業規模を問わず成果を大きく引き上げます。中小企業であっても、補助金・助成金の活用や低コスト施策を組み合わせることで、限られたリソースの中でも質の高い教育を実現することが可能です。さらに、学習を評価制度やOJTに組み込み、ナレッジ共有文化を根付かせれば、学びが日常業務と密接に結び付き、組織全体に好循環が生まれます。
最終的に重要なのは、リスキリングを単なる研修イベントではなく組織文化の一部として定着させることです。管理職の意識改革や心理的安全性の確保といった組織的な後押しがあれば、社員は主体的に新しいスキルを習得し、企業の競争力強化に直結する成果を生み出します。変化が常態化するこれからの時代において、リスキリングは「選択肢」ではなく「必須戦略」であり、その継続的な実践こそが未来の成長を支える最大の鍵となります。