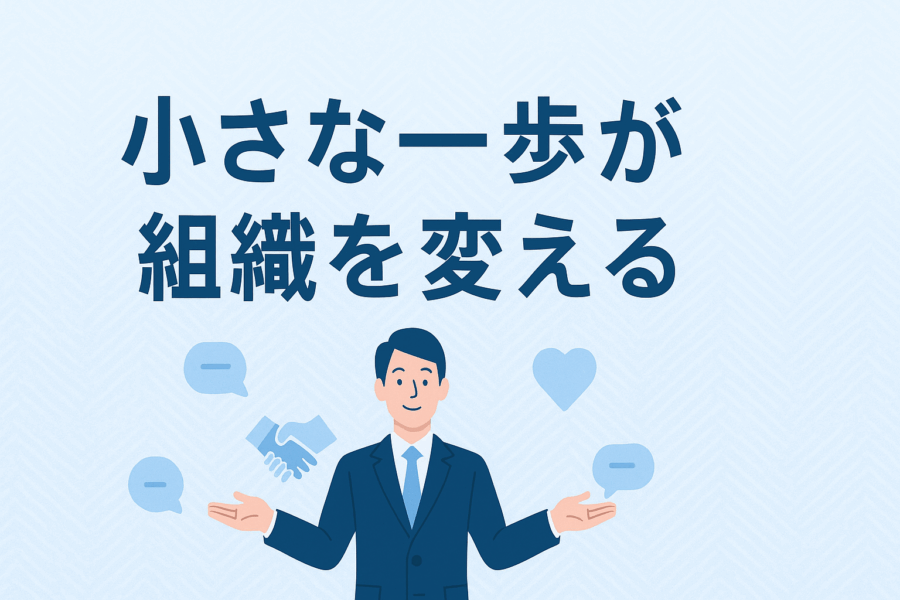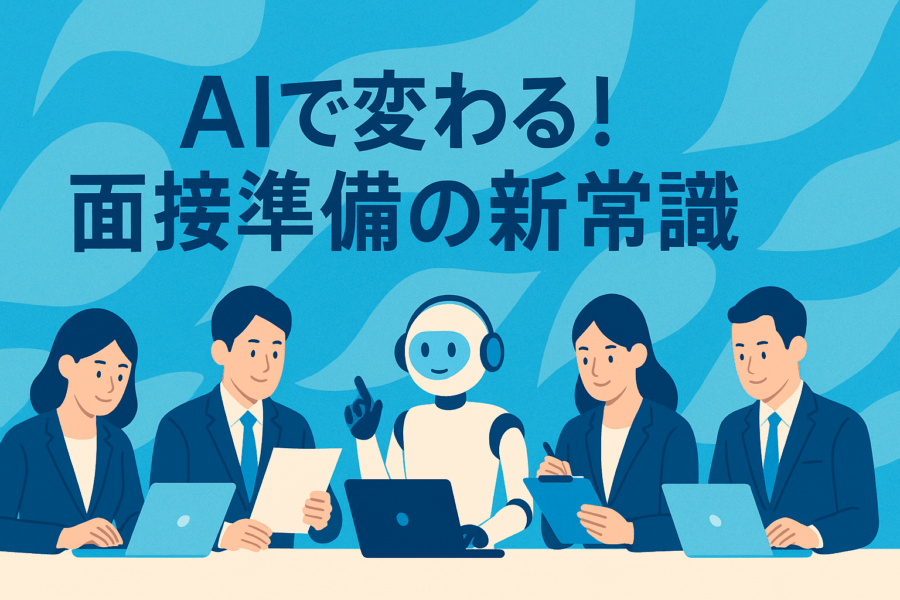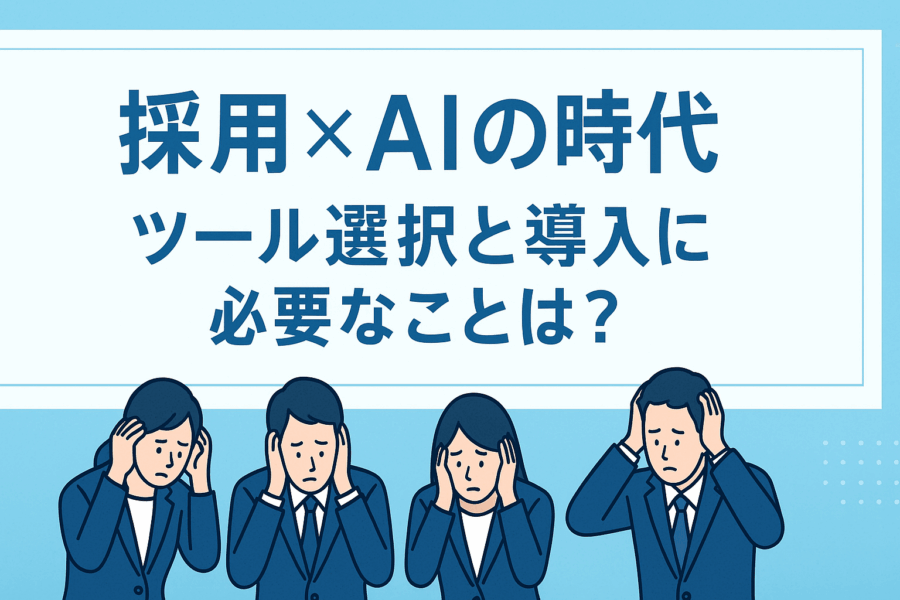更新日
AI
人材採用
面接 で見抜く「嘘と誇張」:AIによる非言語分析と実務での活用ポイントも検証
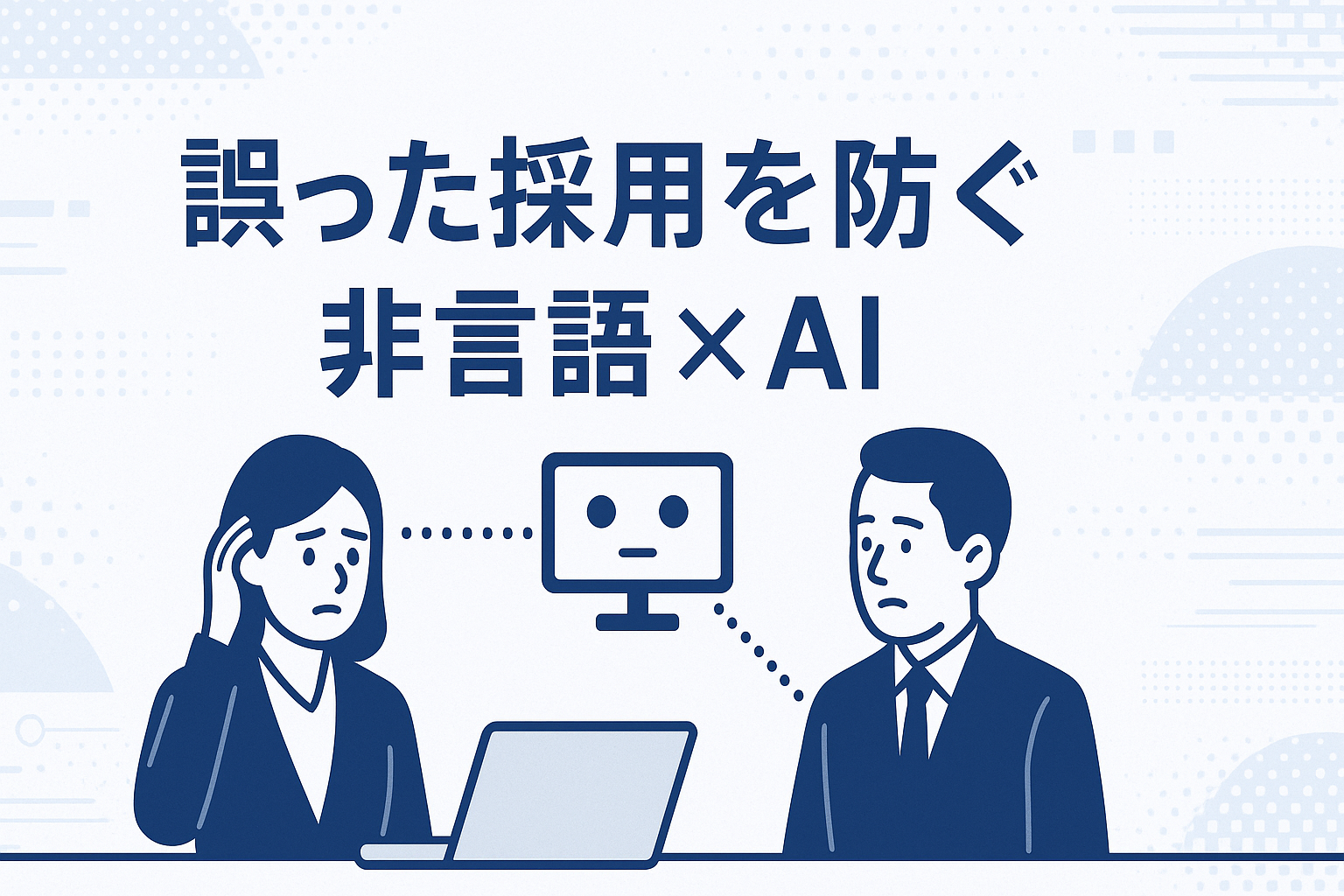
採用 面接 で候補者の 嘘や誇張を見抜くことは、企業にとって重要な課題です。誤った採用は、後々の業務に悪影響を及ぼすことがあり、面接官の見極め力が採用の成否を左右します。
本記事では、嘘や誇張を見抜くための実践的な 面接 手法と、AIを活用した分析の取り組みについて解説します。 面接 の質を高め、ミスマッチを防ぐヒントとしてご活用いただけます。
応募者が事実と異なる発言をする背景には、自分を良く見せたいという心理や、退職理由など話しにくい内容を避けたい気持ちがあると考えられます。職歴や資格、志望動機の誇張、退職理由に関する虚偽などはよく見られる傾向です。
これらを見抜くには、非言語情報の観察が効果的です。さらに、5W1Hを使った質問や行動面接法により、発言の一貫性や具体性を確認しやすくなります。
また、近年はAI技術の活用も進んでいます。たとえば、音声感情解析や表情の変化、声のトーンの分析により、応募者の微細な反応を捉えることが可能です。こうした技術は、人間の感覚では捉えきれない違和感を補う手段として有効ですが、あくまで面接官の判断を補完するものとして活用するのが現実的です。
Contents
嘘や誇張はなぜ起こるのか? 面接 現場の実態とリスク
採用面接の場で候補者が事実と異なる情報を伝えてしまう背景には、「少しでも自分をよく見せたい」という心理があります。とくに競争率が高いポジションでは、自身の経歴やスキルに自信が持てない場合などに、実際よりも良く見えるよう話を盛ってしまうことがあります。しかしこの行動は、単なる印象操作にとどまらず、企業にとって深刻なリスクをもたらす場合があります。
仮に、誤った情報に基づいて採用判断が行われた場合、企業は本来マッチしていた人材を見逃す可能性があり、結果的にチームのパフォーマンスや業績への影響にまで波及することも考えられます。
よくある虚偽のパターン(経歴・資格・志望動機・退職理由)
候補者が面接で用いる典型的な虚偽のパターンとしては、以下のようなものが挙げられます。
・経歴の誇張や捏造:過去に在籍していた企業の規模を大きく見せたり、実際には担当していなかった業務内容を「主担当」として語るケースがあります。役職や所属期間についても、よりよく見えるよう調整されることがあります。
・退職理由のごまかし:ネガティブな理由(人間関係のトラブルや成果未達など)を伏せ、前向きな理由に言い換えることは珍しくありません。明確な根拠なく「新しいチャレンジを求めて」などと回答される場合は、深掘りが必要です。
・資格に関する虚偽:実際には未取得の資格を「取得予定」と表現したり、過去に取得したもののすでに失効している資格をあたかも有効であるかのように伝えるケースもあります。これらは事実確認によって明確に判断できる項目です。
・志望動機の演出:本当は給与や勤務地などの条件面が応募の動機であるにもかかわらず、「御社の理念に共感した」などと強調するなど、本音と建前の差が大きい内容も見受けられます。
こうした事例を見抜くには、曖昧な表現に対して追加質問を投げかけるなどの工夫が必要です。単なる表面的な確認だけでなく、職務内容やスキルに関する具体的な質問を重ねることで、相手の話の一貫性や具体性を評価することができます。
「誇張」と「虚偽」のグレーゾーンと早期離職のリスク
面接では、「多少の誇張」はよくあることと受け止められがちですが、虚偽との境界は非常に曖昧です。たとえば、実際には半年しか担当していなかった業務を「1年以上経験」と表現するような場合、これは事実の脚色にあたります。一方で、全く経験のない業務や、取得していない資格を「経験あり」「資格保有」とするような場合、それは明確な虚偽です。
このような誤りが採用後に発覚した場合、企業側が誤った期待を抱いてポジションを与えてしまうリスクがあります。結果として、実力不足や適応困難が原因で早期離職につながる可能性も高まります。さらに、職場内で「なぜあの人が採用されたのか」という不信感が広がれば、既存社員のモチベーション低下や離職にもつながりかねません。
面接での「嘘・誇張」をあぶり出す質問設計(5W1H × 行動面接 × 深堀り)
面接の場では、候補者が意図的・無意識にかかわらず、話を誇張したり事実と異なることを述べたりするケースがあります。こうした情報の真偽を見極めるには、表面的な質問にとどまらず、構造化された質問設計と深掘りの工夫が必要です。特に、5W1Hの視点を取り入れたうえで、行動面接(BEIやSTAR)や再質問テクニックを組み合わせることで、信憑性の高い情報を引き出すことが可能になります。
5W1Hを用いたヒアリング設計(事実確認の粒度を揃える)
5W1Hとは、「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」「どうやって」の6要素で構成される、情報整理や質問設計の基本フレームです。面接でこのフレームを活用することで、候補者の話の具体性や一貫性を確認することができます。
例えば、経歴を問う際には「どのような役職についていましたか?(What)」「そのプロジェクトはいつ実施されましたか?(When)」「何名のチームで取り組んだのですか?(Who)」など、要素ごとに詳細を掘り下げることが効果的です。こうすることで、回答の粒度を揃え、他候補との比較がしやすくなるだけでなく、曖昧な説明や矛盾点も見えやすくなります。
STAR/BEI法(状況・課題・行動・結果)でエピソードを構造化
候補者のスキルや思考特性をより深く把握するためには、過去の実体験を具体的に語ってもらう質問法が有効です。代表的なものとして「STAR法(Situation/Task/Action/Result)」があります。状況→課題→行動→結果という構造で話してもらうことで、実績の中身や再現性を判断しやすくなります。
たとえば、「前職でのチームマネジメント経験を教えてください」と尋ねた後に、「そのときの状況は?」「課題は何だった?」「どう対応した?」「結果はどうだった?」と段階的に深掘っていくと、話の中に論理の飛躍や不自然な点があれば明確になります。
また、BEI(Behavioral Event Interview)も同様に、過去の行動に焦点をあてて評価する手法であり、抽象的な性格診断よりも職務適性を正確に測る手がかりになります。
時系列での整合性チェック:エントリーシート/職務経歴書との突合
口頭でのやりとりだけでは信憑性を見抜くのは難しいため、エントリーシートや職務経歴書との整合性チェックも欠かせません。とくに、時系列の整合性を丁寧に確認することで、意図的・無意識にかかわらず発生しがちな誇張を見抜くことができます。
たとえば、「2019年からプロジェクトリーダーをしていた」と話す候補者が、職務経歴書にはその時期に別職種が記載されている場合、確認すべきポイントが明確になります。 また、応募書類に記載の無い新たなエピソードが面接中に語られた場合は、面接後のフォローで補足確認を行うことで精度が高まります。
再質問テクニック:同じ事象を別角度から問う、数値と固有名詞で固定化する
「嘘をついている」かどうかは、1回の質問だけでは判断できません。そこで効果的なのが、同じトピックに対して別の角度から質問を重ねる再質問の手法です。
たとえば、「売上を20%増やしました」と話す候補者に対し、「その施策の具体的な中身は?」「実施時期と社内の反応は?」など、観点を変えて掘り下げていくことで、回答の一貫性や具体性を検証できます。さらに、「数値や固有名詞を含む質問」を用いることで、あいまいな説明を避け、現実性のある証言に引き寄せることができます。
「本音の志望動機」「本当の退職理由」を掴む逆質問・追跡質問例
志望動機や退職理由といったテーマは、表面的な説明でごまかされやすい領域です。そのため、一次的な質問だけでなく、背景に踏み込む追跡質問が有効です。
たとえば、「なぜこの職種を選んだのですか?」という問いに対しては、「他に検討していた職種は?」「この選択に影響した出来事はありましたか?」といった補足質問を用いることで、真のモチベーションを明らかにできます。
同様に退職理由では、「なぜ辞めたのか」だけでなく、「退職を決意するまでにどんなことがありましたか?」「その経験から学んだことは何ですか?」といった質問を通して、建前ではなく本音を引き出すことが可能になります。
非言語情報の観察:表情・しぐさ・話し方に注目
面接では、候補者の発言内容だけで評価するのではなく、表情・視線・声の調子・身体の動きといった非言語情報もあわせて観察することが、真実に近づくための鍵となります。とくに、質問への反応が曖昧だったり、エピソードが具体性に欠ける場合は、その言動の裏にある微細な違和感に注意を払うことが重要です。
しぐさ・目線・声のトーンで読み解くサイン
候補者が話しているときのしぐさや表情の変化、目線の動き、声のトーンには、無意識のうちに心理状態が表れます。例えば、具体的な質問に対して言葉を濁したり、説明を急に抽象的に切り替えるような場面では、意図的に何かを隠そうとしている可能性があります。
また、目線の安定性もひとつの判断材料です。話が事実である場合、目線は自然に相手に向きますが、話に自信がない・作り話をしているときには、視線が泳いだり瞬きを繰り返す傾向が見られます。さらに、声のトーンにも変化が現れます。嘘をつくとき、人は緊張や不安から声が通常より高くなったり、不自然に低くなったりすることがあります。
これらの変化を一つひとつ単独で判断するのではなく、話の内容と非言語的な反応を組み合わせて観察することで、信頼性の有無をより立体的に把握できます。
面接官が陥りやすい「思い込み」と「バイアス」
候補者の誠実さを見極めるうえで、もうひとつ重要なのが面接官自身が持つ先入観や判断の偏りを自覚することです。いわゆる「バイアス」や「思い込み」は、候補者の本来の資質を正しく評価する妨げになります。
たとえば、学歴や職歴による評価の偏り(学歴バイアス・職歴バイアス)や、第一印象が良いというだけで実力以上に評価してしまう「第一印象バイアス」などが挙げられます。これらのバイアスが強く働くと、非言語的なサインを正確に読み取る目も曇りがちになります。
そのため、面接を実施する際にはあらかじめ評価基準を明文化し、できる限り複数人で評価を行う体制を整えることが有効です。評価者同士で視点を共有し、一人の主観に偏らないような仕組みを持つことで、候補者の発言の真偽や意図を客観的に把握しやすくなります。

AI分析の可能性と限界:嘘検出ツールは信頼できるか?
近年、AIによる分析技術は採用現場でも注目を集めており、とくに候補者の嘘や誇張を見抜く手段としての可能性に期待が寄せられています。しかし、どんなに技術が進化していても、過信は禁物です。AIを用いた分析はあくまでも補助的な役割であり、最終的な判断には人間の経験と洞察が欠かせません。
音声感情解析・表情認識の進化と活用ポイント
AIが面接支援において注目されている理由のひとつが、音声感情解析と表情認識技術の急速な進歩です。
音声感情解析では、候補者の声のトーンや抑揚、話すスピードや間の取り方などを分析することで、緊張や不安、自信の有無といった感情の兆候を読み取ることが可能です。たとえば、過度に早口になったり、声のトーンが不自然に高まるといった反応は、ストレスや嘘の兆候と関連付けられることがあります。
一方、表情認識技術では、顔の微細な動きや変化から、候補者の心理状態を推測できます。具体的には、質問に対して一瞬眉間が動く、笑顔がぎこちない、目線が頻繁に逸れるといった動作がAIにより自動検出され、感情の揺らぎを数値化することができます。
こうした技術をAIがリアルタイムで解析し、複数の候補者の反応を定量的に比較できることは、従来の人間の観察に比べて明らかな利点です。音声と表情のデータを組み合わせることで、候補者の言動に対する多角的な分析が可能になります。
AI分析の限界──過信せず、補完的に活用する
ただし、こうした技術には明確な限界もあります。たとえば、緊張によって声や表情に変化が生じるのは、嘘をついているからとは限らないという点です。文化的背景や個人の性格によって、非言語表現の傾向は大きく異なります。
そのため、AIの出す「ストレス反応あり」といった解析結果を鵜呑みにして即判断することはリスクが高く、面接官による補完的な評価が不可欠です。候補者の過去の経験や書類の内容、職務適性といった要素と総合的に組み合わせて判断する必要があります。
AIの導入によって面接の精度が向上することは間違いありませんが、最終的な判断を下すのは人間であるという前提を忘れてはなりません。
法的・倫理的な留意点──導入時の「落とし穴」を回避するには
AI技術を採用面接に導入する際には、法的・倫理的なリスクを慎重に検討する必要があります。
たとえば、実際にあったケースでは、候補者が学歴詐称をしていたことが入社後に発覚し、重要プロジェクトの信頼性が揺らぐ事態に発展しました。こうしたトラブルを防ぐためにAIを活用するのは有効な手段ですが、候補者の個人情報(音声・映像データなど)を扱う場合、プライバシー保護の観点からも細心の注意が求められます。
・本人の同意なしにデータを取得・解析することはNG
・データの保存・管理・利用範囲を明確にし、第三者に漏洩しないよう対策を講じる
・誤検出による不当な評価が発生しないよう、アルゴリズムの透明性を担保する
また、導入前に法務部門や外部の弁護士と連携し、利用規定や責任範囲を明文化することも推奨されます。候補者への通知義務を明示し、AI分析の存在を事前に説明することで、面接の透明性や候補者の納得感も向上します。
AIと人間の協働による、公正で信頼性の高い採用へ
AIによる分析は、面接官の判断を補強する優れたツールです。しかし、それ単体で正解を出すものではありません。候補者にとっても、企業にとっても、公平で信頼性の高い選考プロセスを実現するためには、AIと人の役割を明確に分けたうえで、互いを補い合う設計が不可欠です。
技術を活用するからこそ、「人としての判断」が問われる時代になったとも言えるでしょう。企業はAI導入の利点だけでなく、その運用に伴う責任や配慮すべき点も含めて正しく理解し、戦略的に活用する必要があります。
※他にもAIを活用した面接に関する記事がございます。是非こちらもご覧ください。
見抜くだけでなく「見極める」面接へ:実務改善のヒント
面接において、嘘や誇張を見抜くことは確かに大切ですが、企業が本当に求めるべきは、候補者の本質的な力と将来性を見極めることです。そのためには、「嘘を排除する」ことにとどまらず、信頼性の高い情報を引き出し、入社後の活躍に結びつける視点が必要です。
このような面接の質向上に向けては、評価基準の見直しと面接フローの改善が出発点になります。
嘘を防ぐプロセス設計と評価フォーマット
面接での誤判断を減らすには、事前準備から当日の運用、評価記録まで一貫したプロセス設計が求められます。
まず、候補者のレジュメや経歴を面接前に十分に読み込み、質問の焦点を絞っておくことで、当日の質問が表面的にならず、矛盾や不自然さにも気付きやすくなります。
質問設計では、これまで述べたように5W1HやSTAR法などの構造化フレームを活用することで、発言の裏付けとなる事実を引き出しやすくなります。加えて、書類との整合性チェックや、非言語情報(視線・声・表情など)の観察を組み合わせることで、より多面的に候補者の言動を評価できます。
また、面接官自身の先入観を排除する仕組みも不可欠です。面接官が複数いる場合には、共通の評価フォーマットを導入し、同じ観点で評価を行うようにすることで、個人の印象に偏らない判断がしやすくなります。
これらのプロセス整備は、単なる面接手法の改善にとどまらず、組織の採用力そのものを底上げする実務改善の柱となります。
面接〜入社後のパフォーマンスをつなげる評価の仕組み
採用活動のゴールは「内定」ではなく、入社後にその人材が活躍できるかどうかです。そのためには、面接時に得られた情報を、入社後の人材育成や評価の仕組みにしっかりとつなげることが重要です。
まず、面接で聞き出した内容は、評価シートや記録として体系的に残しておきましょう。たとえば、候補者が語った強みや、過去の成功経験、得意な仕事の進め方などを整理しておくことで、その人が実際にどう貢献できるかの仮説を立てやすくなります。
入社後には、上司やチームからの定期的なフィードバックを取り入れ、定量的な成果と定性的な行動面の両面から評価を実施します。これにより、面接時の自己申告とのズレがある場合には、早期に気づいてフォローアップすることができます。
さらに、面接時の評価と実際のパフォーマンスとの「差分」を確認するための評価会議を定期的に設けるのも効果的です。このプロセスを通じて、「こういった発言をしていた人は実際に活躍しやすい」といった採用側の知見も蓄積され、次回以降の面接の質向上にもつながります。
まとめ:嘘を見抜くから、真の価値を見極める面接へ
採用面接は単なる“選別の場”ではなく、候補者の本質を見極め、企業との最適なマッチングを図るための重要なプロセスです。
本記事で紹介したように、嘘や誇張の見抜き方には、質問設計の工夫、非言語情報の観察、AIの補助的な活用など多様な手段があります。しかし、それらの手法の目的は「排除」ではなく、「見極め」にあります。
候補者の過去の行動や発言の整合性を丁寧に検証しながらも、未来に向けた成長の可能性に目を向ける視点こそが、面接の本質です。そしてその実現には、面接の精度を支える評価プロセスの整備と、入社後の育成・評価との接続が欠かせません。
テクノロジーの力を活用しつつも、最終的な判断には人の目と感性が不可欠です。
“疑う面接”から“信頼に基づく対話”へ。候補者の言葉の奥にある真意をくみ取り、組織にとって本当に必要な人材を見極める力が、これからの採用に求められています。